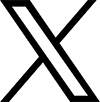御三家にみるバスクシャツの吸引力。
ところで日本語には「御三家」という言葉がある。ある分野において、きわめて優れている、または名を馳せている上位の三者を指す表現だ。
バスクシャツという定番アイテムにもまさしく御三家と称されるブランドがある。したがって『knowbrand magazine』において、バスクシャツ御三家の出自やデザインの由縁、魅力を探ってゆかぬわけにはいかないのである。
バスクシャツの正体。
ラフな風合いの厚手のコットン生地、浅い船底のように横に広くあいた「ボートネック」と呼ばれる襟、少し短めの袖丈、そして日本では一般的にボーダーと称される青と白二色の横縞。こういったデザインディテールを有したカットソー。これが「バスクシャツ」という言葉を知っている者であれば誰しもが抱くイメージではないだろうか。
バスクシャツは「可愛い」とさえ表現されがちなフレンチカジュアルを代表するファッションアイテムである。しかし、そのルーツは、可愛さとは無縁だ。フランスとスペインにまたがる海辺のバスク地方で16世紀頃から漁師や船乗りたちが着ていた作業着だったといわれているのだ。したがって、そのディテールにはそれぞれ意味がある。厚手のコットン地は、衣類としての耐久性と海風対策を兼ね備えるための必然であり、ボートネックは濡れた際にも脱ぎやすく、短めの袖丈は袖口の水濡れや作業時の器具への引っ掛かりを防げる。そして横縞のボーダー柄は、海に転落した際に目立ち発見しやすいため取り入れられたともいわれている。つまりは機能性に裏打ちされた意匠というわけだ。しかもその機能性の高さは実証されている。バスクシャツは1850年代から現代にいたるまで、フランス海軍のユニフォームとして採用されているからだ。
もうおわかりだろう。そのキュートな見た目に反し、バスクシャツの正体は、タフで実用的なワークウェアであり、ミリタリーウェアなのである。
このバスクシャツが、ファッション化し始めたのは1920年代だといわれている。フランスに居を構え、ファッショニスタとしても知られていたアメリカ人画家ジェラルド・マーフィがバスクシャツを海辺でのリゾートファッションに取り入れたのが発端というのが有力だ。彼の友人であった画家のパブロ・ピカソや小説家のアーネスト・ヘミングウェイといった巨匠たちもその影響を受け、バスクシャツは文化人をはじめ、南フランスのセレブリティの間で流行、やがてファションとしての市民権を獲得していったようである。
さて御三家である。少なくとも日々の装いに少なからずの興味を持ち、ファッションアイテムとしてバスクシャツを手にするのであれば、その御三家たる三大ブランドは避けては通れないだろう。もちろんいずれのブランドもフランス海軍にバスクシャツを納入した実績を誇っているだけに、質の高さは折り紙付きであることは先に断っておこう。
バスクシャツ御三家筆頭の
老舗ブランド。
御三家の筆頭は、〈SAINTJAMES セントジェームス〉をおいてほかにない。
セントジェームスの創業は1889年とかなり古い。当然、御三家の中の最古参であり、地元の漁師や船乗りのためにウール製のマリンセーターを生産していたところからその歴史はスタートする。このマリンセーターが原型となり、生地をコットンへと変えバスクシャツが誕生することとなる。
バスクシャツの中でも同ブランドを代表する定番中の定番モデルが「ウェッソン」だ。

〈SAINTJAMES〉の定番モデル「ウェッソン」
誰しもが頭に思い浮かべるバスクシャツのイメージそのものではないだろうか。
御三家で最古参のセントジェームス。その歴史の長さはロゴマークにも表現されている。そこに描かれているのは、世界遺産として名高い海に浮かぶ孤島の修道院「モン・サン・ミッシェル」だ。

タグの左部に世界遺産「モン・サン・ミッシェル」が描かれている
創業当初の同社マリンセーターは、モン・サン・ミッシェルの干潟の牧草を食べ育った羊からとれた毛でつくられていたといわれ、その歴史への敬意と誇りから同社のロゴのモチーフにもなっているのだ。
オトナたるもの質の高さや風合いにこだわることが大切だ。程よく色落ちしたインディゴブルーのストレートジーンズに、洗いざらしのセントジェームスのウェッソン。色はブルーボーダーを。長き歴史をもつマリンワーカー由来の質実剛健さを肌で感じることができる。

日本に紹介されたのは1980年代といわれているセントジェームス。同社が誕生したのは、モン・サン・ミッシェルにほど近いフランス ノルマンディー地域マンシュ県の街「Saint-James」。フランス語に準じ日本語表記すると「サン=ジャム」となる。そう、日本ではセントジェームスの名でお馴染みなのだが、実はこれは英語読みなのだ。
そんな意外な事実も含めて、様々なバックボーンを持ち合わせている老舗だからこそ、日本のみならず世界中で長きにわたりバスクシャツの代表ブランドとして変わらぬ人気を誇っているのだろう。
バスクシャツ御三家 随一の希少性。
御三家のふたつ目は創業当時からの現在にいたるまで、生地の生産から縫製までを一貫してフランスの自社工場でおこなうことにこだわり続けているブランドだ。1936年にフランス北西岸ブルターニュ地方で、誕生した〈Le minor ルミノア〉である。

フランスの自社工場での生産を貫く〈Le minor〉のバスクシャツ
同社の品質へのこだわりは、フランスメイドを貫いているという点だけでない。自社製品の品質を維持するために、ビジネスを肥大化させず小規模にとどめつづけているのだ。それゆえ年間の生産数はおのずと限られており、希少性という面では、バスクシャツ御三家の中で随一といわれている。

〈Le minor〉は、品質維持のためにスモールビジネスに徹する
また他社に比べてカラーバリエーションが豊富なことも魅力のひとつ。その色数は400色以上とも言われており、ひと味違ったテイストの一着を探すという楽しみ方ができるのはルミノアの大きなアドバンテージだろう。

フレンチムードがグッと高まる赤のボーダーにホワイトデニム
ちなみにバスクシャツという呼称だが、本場フランスでは、ほぼ通じないということをご存じだろうか。実際には「ブルトンマリン」と呼ばれることが一般的なのだという。ルミノアの創業の地でもある「ブルターニュ地方のマリンシャツ」という意味だそうだ。日本ではバスクシャツ、フランスではブルトンマリン。このあたりの呼称の違いが生じたいきさつには諸説あり、その由来もはっきりとしない。いやむしろその曖昧さこそが、歴史ある定番アイテムだけがもちうるロマンなのだ。
バスクシャツ御三家で最も贅沢な生地。
バスクシャツ御三家の最後は〈ORCIVAL オーシバル〉だ。創業は1939年、ブランド名はフランス中部にある小さな村の名にちなんだものだという。
オーシバルのバスクシャツとして最もポピュラーなのが「RACHEL ラッセル」である。

〈ORCIVAL〉の定番モデル「RACHEL」
肩や胸元と裾が無地になっているお馴染みのルックス。これは「パネルボーダー」と呼ばれており、このパターンこそがフランス海軍が採用してきた意匠なのだ。その理由は定かではないが、パネルボーダーは海に転落時した際に通常のボーダーにくらべてより視認性が高かかったため、ということは考えられるだろう。
ところで先述の2ブランドにもパネルボーダーのモデルは存在するわけだが、オーシバルのそれの場合、その生地に注目したい。アイテム名のラッセルは、フランスでも数台しかない貴重な編機で生産される「ラッセル生地」に由来している。縦方向に整形された糸をループで絡み合わせた編み組織でできており、一般的なカットソーの生地に比べ複雑な構造なのだ。そのため糸を多く使う上、編むのにも時間を要する。よって御三家の中で最も贅沢な生地を使用しているといえる。もちろんその分、高品質だ。丈夫でいて通気性も良い。独特なハリ感を有しており、着込むほどに体に馴染み、風合いも素晴らしい。

〈ORCIVAL〉のアイデンティティともいえるラッセル生地

フランス海軍採用のパネルボーダーは、ミリタリーテイストのパンツとの相性も良い
ちなみにオーシバルのアイコンでもある蜜蜂のエンブレム。蜜蜂は自分の巣に正しく帰ってくる帰巣性が高く、出兵した海兵たちに向けて必ず生きて帰って来きて欲しいというメッセージが込められているとの説もある。実際には、軍用装備品としてのバスクシャツに蜜蜂のエンブレムは不要であり、信憑性は極めて低い説だが、こうしたエピソードが存在すること自体もオーシバルのもつ魅力のひとつとしてとらえようではないか。

裾には蜜蜂のエンブレム。サイドの深めのサイドスリットは腰周りの動きやすさを考慮したもの
コーディネートに迷ったとき、とりあえずボーダーをチョイスする。これは揺るぎないひとつの答えだ。
その一枚をコーディネートにトッピングするだけでマリンルックが完成してしまう。ボーダーのバスクシャツはそれほどの力をもったキーアイテムである。

だが、爽やかなルックスに反して、そのつくりはいたって堅牢である。太い番手の糸が使われた目の詰まった厚手の生地は、いかにも海で働く者のためのワークウェアであったことを物語るタフさの象徴だ。
もちろんへたりにくい。着込み、洗いをかけるほど身体に馴染み、だから愛着も増す。
街ですれ違う人々と「ボーダーかぶり」することなどざらである。だからとて着ることをやめることはないだろう。いやむしろ、やめられないといった方が正しい。いずれ我々を惹き付けてやまないボーダーのバスクシャツは、それだけファッションアイテムとしての吸引力を持ち合わせている。
そして海を感じさせる初夏の抜けるような青空に、きょうもまたバスクシャツを手にとるのだ。