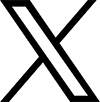ワールドクラス・ジャパン“セカイに誇るニッポンのモノ” 〜〈コム デ ギャルソン〉黒の自由 篇〜【vol.01】
2019年にブランド誕生から50周年を経て、いまなおトップランナーとして、我が国のファッションシーンをけん引し続けるコム デ ギャルソンとデザイナー・川久保 玲。時に“孤高”“唯一無二”“破壊者”とも評される稀代の天才は、その長い歴史と成長の過程で、数々のブランドを生み出してきた。今回は、時代と共に奔放に広がっていった血脈を、各年代の事件や流行などを絡めつつ、誕生順に紐解いてゆこうと思う。
固定観念に囚われない“自由”な発想や、物事に対する見方、そして何よりブレず貫き通してきたクリエイションとその姿勢へのリスペクトを込めて……今こそ知るべきコム デ ギャルソン。
1969年
〈COMME des GARÇONS
コム デ ギャルソン〉。

その始まりは1969年。アポロ11号が人類初の月面着陸に成功し、日本国内では、東名高速道路が全面開通し、人々の暮らしにも大きな影響を与えたこの時代に、新たなレディースブランドがひっそりと産声を上げる。街行く若者たちの間では、マイクロミニスカートとロングスカートが流行し、パンタロンスタイル全盛。翌1970年には大阪万博も控えた、俗にいう高度成長期の真っ只中のことである。デザイナーは、もはやファッション界の生きる伝説ともいえる川久保 玲。
1942年・東京生まれ。慶應義塾大学の文学部哲学科で美学を専攻し、卒業後、繊維会社の宣伝部を経て、フリーのスタイリストとなった彼女は、自身の感性に響く服になかなか出会えなかったことから、独学でデザイン・パターン・縫製・仕上げまでの全てを手掛ける服作りを始めた。これこそが〈COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン〉である。
初期はシンプルだったようだが、1981年のパリコレ初参加時には、アシンメトリーなデザインで生地を切りっぱなしで使ったり、穴を開けたりツギハギした服を発表し、人々を驚かせた。こうして革新の旗手は“自由と反骨精神”を糧に、衣服の既成概念を覆すアバンギャルドなクリエイションを提示していく。ジャケットやドレスの再構築、テキスタイルの開発、パッチワーク、斬新なパターニング…etc.。こうした今に続く同ブランドの代表的手法の数々が、世界中のデザイナーたちに多大な影響を与えることに。それは水面に落とした墨汁の一滴が、波紋とともに広がっていくさまのようでもあった。こうして川久保は、モードの世界で確固たる地位を築いていく。

2003 SSシーズンのコート「GK-C006」。布の密集は、同ブランドで頻出する手法の1つ。何層にも折り重なった生地の生み出すドレープは、たおやかでいながら力強い意志を秘め、禁欲的なはずの黒を華やかな印象へと変えている。

2010 SSシーズンモデルのジャケット「GE-J037」。パッチワークを駆使して再構築されたボディは、左右非対称ながら破綻することはなく、その歪さの中から覗く可愛らしい水玉模様も相まって、パンキッシュな趣きをより強いものに。
ではここで、話をブランドヒストリーへと戻し、時計の針を3年後の1972年へと進めてみよう。当時の大きなトピックとしては、日本列島改造計画を唱える田中角栄内閣発足が挙げられる。さらに日中国交正常化により来日したパンダ2頭が上野動物園で公開され、一目見たさに黒山の人だかり。一方では、連合赤軍による、あさま山荘事件が起きるなど、まさに激動と呼ぶに相応しい時代。続く1973年には、原油高騰が招いた経済的混乱、第一次オイルショックが発生したことで自然志向が強まり、大量生産・大量消費を否定する“チープ・シック”という概念も誕生。さらに1950年代から続くベトナム戦争に対する反戦ムードの中で生まれた“ヒッピームーブメント”の影響から、ジーンズスタイルが大流行。この頃から、カウンターカルチャーとファッションが明確に紐付いていったといえる。
このように世の中は不況の中にあったものの、1970年代はファッションが盛り上がりを見せた時代でもある。川久保が同年、「株式会社コム・デ・ギャルソン」を設立しているのはその証左といえる。栄枯盛衰のファッション業界において誕生から50年を経てなお、強くて新しいものを求める姿勢を貫き続け、時代を切り拓き続けるコム デ ギャルソンの血脈。その礎がここに築かれたのである。そこから2年後の1975年。約20年続いたベトナム戦争がサイゴン陥落とともに終結を迎えたのと時同じくして、東京・原宿でブランド初のファッションショーを開催。同年、表参道に初の直営店をオープンさせる。
ところでこのブランド名についてだが、当時は〈HANAE MORI ハナエモリ〉や〈KENZO ケンゾー〉などのように、デザイナー自身の名を冠するのが主流。そんな中で川久保は、フランス語で“少年のように”を意味する言葉を冠した。何故なのか? その理由は“ただ言葉の響きが好きだったから”だそうだが、のちに「今思うとなるべく作った服が表に出て、作った人は表に出ない方がいいと単純に思っただけ」とも語っている。例えば、『星の王子さま』という物語の素晴らしさを語る際に、作者自身について言及する必要があるか。いや、ないだろう。それよりも創作における重要性は、これまでも誰も目にしたことのないもの、まったく新しいものをどんなふうに、どんなやり方で表現することができるかにある。“生み出されたものの中に、全てが込められている”という確固たる信念のもと、黙々とクリエイションを続けている彼女の根幹たる部分が、この詩的で響きの良いブランド名から強く感じられるのだから、これもまた真なり。
1978年
〈COMME des GARÇONS HOMME
コム デ ギャルソン・オム〉。

世界と日本を結ぶ空の玄関口、新東京国際空港(現成田国際空港)が開港。日本中の喫茶店では、ビデオゲーム『スペースインベーダー』が大流行。大人も子供も、電子音と紫煙に包まれながら、宇宙から飛来した極彩色の侵略者と戦い、原宿では竹の子族と呼ばれる奇々怪々な集団が、ディスコサウンドに合わせて踊り狂う1978年。直営店オープンで勢いを増すコム デ ギャルソン社は、初のメンズライン〈COMME des GARÇONS HOMME コム デ ギャルソン・オム〉を発足する。
“GOOD SENSE GOOD GUALITY”をキーワードに掲げた同ブランド。元々は川久保自身がデザイナーを務めていたが、変遷を経て、2003年から渡辺淳弥にバトンタッチ。初期からフルラインを展開し、そのコンセプトを一言で表すならば、“良い素材、良い縫製、良いパターンによる服作り”。当時巷で流行っていた、アメリカ西海岸の快活なサーファースタイルとも、ヨーロッパ調のフェミニンなスタイルとも異なり、シルエットはいわば古式ゆかしいボックス型。色は男の定番色であるブラックやグレーにネイビー。あくまでスタンダードを踏襲した上で、ギャルソン流のアレンジが加えられたアイテム群は、DCブランドが作るデザイン過剰な服に飽きた人々の目に、新鮮なものとして映ったようだ。

2018年製作モデルのテーラードジャケット。ボディと同色の数種類のファブリックをパッチワークすることによって、ブラック一色ながらも立体感を創出。クラシカルなボックスシルエットのジャケットが今日的で表情豊かなアイテムに。
同ブランドの中では、シワ加工を施したシャツがアイコンとして知られているが、ここで掲載するのは、2018年に製作されたテーラードジャケットだ。オーソドックスな3ボタンのテーラードながら、数種類のファブリックでパッチワークを施すことで、ツイストが効いている。時代とともにパターンや素材感は変化するものの、着る者の個性を生かすデザインは今も健在である。
1981年
〈tricot COMME des GARÇONS
トリコ・コム デ ギャルソン〉。

アメリカでレーガン大統領暗殺未遂事件が起き、カリブ海に浮かぶ島国では、“レゲエの神様”ボブ・マーリーが死去。女王が統治するイギリスでは、チャールズ皇太子とダイアナ・スペンサーの結婚が報じられた。そんな悲喜交々の中で、多種多様なカルチャーが一斉に花開き出した1981年4月、コム デ ギャルソン社は、パリの歴史を彩ってきた5つ星ホテル「インターコンチネンタル パリ ルグラン」のサロンで、デビューコレクションを開催する。イギリスやアメリカにある世界有数のショップのバイヤーが目撃したそのショーは、すでに日本である程度の成功を収めていたギャルソンによる12年目の新たなチャレンジであり、のちのパリ進出の第一歩であった。
この偉業を語るならば、同時期にスタートさせた〈tricot COMME des GARÇONS トリコ・コム デ ギャルソン〉にも触れておかねばなるまい。通称“トリコ”。フランス語で「編み物」を意味するtricotの名前が示す通り、当初はニット類にのみ特化したブランドとしてスタート。数年後には布帛を用いたTシャツも展開するようになり、バトンが川久保から渡辺淳弥へと受け継がれた1987年には、当時の同社における国内年間売上のトップを誇るブランドにまで成長を遂げる。ちなみに、〈kolor カラー〉のデザイナーとして活躍する阿部潤一が、1989年にコム デ ギャルソンに入社して最初に配属されたのが同ブランドだったとか。そう聞けば、“時代のニュアンスやムードといった言語化が難しい感覚の具象化すること”を重要視しているという、彼のクリエイションの原点がここで学んだものであるということは、想像に難くない。

2019 SSシーズンモデルのスカート「TC-S203」。ウールとレースで切り替えた左右非対称のボディを染めるのは、何者にも染まらない色である黒。大人の表情という横糸と可愛らしさという縦糸で編み上げられたユニークな1着。
2002年には、阿部と同じく、渡辺のもとでクリエイションを学んだ栗原たおが、デザイナーに就任。現在ではフルラインを展開するブランドへと拡大化した同ブランド。その特徴は“ガーリー”と表現されることが多く、彼女の個性が光るアイテムとしては、このスカートなど実に面白い。ウールとレースを切り替えたアシンメトリーなシルエットは、少女と大人の女性との間で揺れ動くかのような危うさを感じさせながら、日常的に着やすくもある。この歪みとも呼べる揺らぎこそ、コム デ ギャルソンの真骨頂といえよう。
1982年
「黒の衝撃」。
〈EDWIN エドウィン〉によって開発されたストーンウォッシュのジーンズが流行し、白銀に輝く500円硬貨が姿を現した1982年。社会の仕組みの中心にある貨幣とファッションに変化が訪れたその頃。コム デ ギャルソンがパリコレに参加して3シーズン目となる同年3月のコレクションにおいて、モード界に激震が走る。
それは事件だった。ギャルソンと同じく日本からやってきた〈yohji yamamoto ヨウジヤマモト〉の両雄が、全身を黒一色で覆ったコレクションを発表したのである。それまでのモード界では死や反抗を意味し、タブー視されていた“黒”。もちろん誰もハイファッションに用いることなど考えもしなかった時代“なのに”である。
特にギャルソンのコレクションは誰の目にも異質だった。黒の色彩に、左右不揃いでしわくちゃ、ところどころ引きちぎられ、穴が空き、肌があらわになった生地が、シンプルながら大胆なカッティングにより、柔らかな身体のラインをすっかり覆い隠す。“ボロルック”と称された奇妙な服たちは、性別という枷から女性を解き放つと同時に、それまでの華美で色鮮やかな高級志向に満ち溢れていたパリコレに、真逆の“美”を突きつけた。目の前を通り過ぎるモデルたちを見たショーの観客たちは、そのあまりの衝撃に唖然としたという。凝り固まったモードの世界へ打ち下ろされた強烈なインパクトは、“黒の衝撃”と報じられ賛否を巻き起こす。新たな美の到来に対する賛辞の言葉だけではなく、長い歴史の中で育まれてきた西洋の“伝統的”衣服文化を破壊するものであるとして、皮肉を込めた辛辣な評価を下すメディアもまた多かったのだ。
だが彼女は、己が美しいと思ったものを、表現したに過ぎなかったのではないか。ただそれが当時としては、いささか斬新過ぎたということだろう。しかし既知の世界において、新たな試みを行う者の前には、常にいばらの道が続いているもの。川久保は言う「無視されるよりも、けなされたり避難される方がまだまし。とにかく批評が存在していることが刺激になった」と。自分らのクリエイションにより引き起こされたリアクションと両極な評価を、彼女は力強く前へと進む糧へと変えていったのである。
とにもかくにもコム デ ギャルソンは、“黒の衝撃”により伝統や常識という揺るぐことなき旧来の美意識の前に、衣服の新たな解釈や可能性、いわばファッションの”自由“な表現や捉え方を突きつけたのではないだろうか。その証拠に、モード界は最も洗練された色として“黒”を享受し、今や社会的常識となった。まさに“黒”がもたらした“自由”というわけだ。余談ではあるが、現在でもコム デ ギャルソンの展示会でのオーダーシートの1番色は“黒”だという。

2015年、雑誌『SWITCH』(VOL.33 NO.3)で組まれた、特集記事内のインタビューにおいて、インタビュアーの投げかけた、「どんな仕事のあり方を自分に課しているのか?」という問いかけに、「結局新しいものを作るということです。そして作り続けるということだけです」と答えている川久保。“黒の衝撃”。それは今から遡ること38年前。未知への開拓にこそ価値を見出してきた彼女が残した大いなる轍。その出発点の記憶を人々の脳裏に焼き付け、コム デ ギャルソンは次なるフェーズへと歩みを進める。
続くVol.02では、日本がバブル景気に湧く前夜の1984年に誕生した、〈COMME des GARÇONS HOMME PLUS コム デ ギャルソン・オム プリュス〉から、90年代に川久保の好きなスタイルをベースとして生まれたコレクションライン、〈COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン・コム デ ギャルソン〉までをクローズアップ。日本と世界、そして日常とモード、ひいてはファッションとアートというボーダーを超えて、さらに強さと鋭さを増していくクリエイション。“黒の衝撃”以降、コム デ ギャルソンが切り開いていった“未知”とは?
(→【vol.02】につづく)
(→〈COMME des GARÇONS〉に関連する別の特集記事は、こちら)