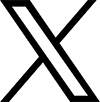「バーキン」「ケリー」…etc.〈HERMÈS エルメス〉はなぜ革製品にこだわるのか?「デュックとタイガー」に秘めた思い。
数あるラグジュアリーブランドの中でも、格上のイメージを持つ方も多いのではないだろうか。
その象徴ともいえるバッグが「純金よりも投資価値がある」とすら言われることもある「Birkin バーキン」だ。
このバッグの価値を高めている理由のひとつが、その希少性であることは知る人も多いだろう。
熟練した職人が全ての工程を担当し、革の切断から縫製、組み立てに至るまで手作業で作り上げるという、現代では珍しい工程によって制作されるバーキン。優秀な職人の数は限られているために、制作可能な個数は限られてくる。その結果、需要に対する供給が追いつかないということになり、希少価値が高いアイテムとなっているのだ。
だが、それだけではこのバーキンの魅力を説明していることにはならないだろう。
そもそも人々はなぜエルメスというブランドに魅せられるのか?
今回の『knowbrand magazine』では、世界の最高峰のブランドのひとつであるエルメスの魅力と、その秘密に迫ってみようと思う。
高級馬具を製造する
工房としてスタートした
〈HERMÈS エルメス〉。
〈HERMÈS エルメス〉の歴史は、ティエリー・エルメスが1837年、高級馬具を製作する工房をパリ9区に開いたところからスタートする。
その工房の技術は当初から高く評価され、1867年および1878年のパリ万博では、それぞれ銀賞・金賞を受賞するほど。1880年には、現在もその地に本店を構えるエリゼ地区のフォーブ ル・サントノーレ24番地にブティックを移転。それと同時に顧客への直接販売を開始し、審美眼の厳しいパリ市民にも認められていくこととなる。
「BIRKIN バーキン」の原型が誕生、
そしてハンドバッグの製造を開始。
1892年には、サドル・バッグ(馬の鞍を収めるカバン)として「haut-à-croire オータクロア」を制作し、販売を開始。あくまで馬具を収納するための道具であったこのバッグだが、その佇まいは改めていま見ても美しい。このバッグを原型として、およそ100年の時を経たのち、伝説的傑作「BIRKIN バーキン」が生まれることとなる。
その後エルメスは、1900年、ロシアのサンクト・ペテルブルグへと赴き、ロシア皇帝ニコライ 2世に馬具と鞄を売り込むことに成功。これを機に、エルメスは世界的な馬車商へと発展していく。それからしばらく経つと、アメリカを皮切りに自動車が市民の足として普及してゆくことになる。
交通手段が馬車から車へ移行してゆくにつれ、馬具の需要縮小を予見したエルメスは、馬具以外の製造・販売にも手を広げ、その事業を拡大。上質な革を入手するルートと、高度な技を持つ職人という武器を駆使し、婦人バッグや財布などの皮革製品を開発、1920年には社内にハンドバッグ部門を新設。さらに腕時計や洋服・アクセサリー・香水などの分野にも手を広げ、世界のファッションをリードしてゆく。

〈HERMÈS エルメス〉で初期に製作されていたベルトである乗馬の際に使用するあぶみを鞍(くら)に繋げておく「あぶみ革」の「エトリヴィエー¥」をあしらった「ETRIVIERE DOCUMENT エトリヴィエール ドキュメント」。
世界で初めてバッグにファスナーを採用した
〈HERMÈS エルメス〉の
「BOLIDE ボリード」。
エルメスの伝統と歴史の上で、バーキンと並んで欠かせない存在といえるのが「BOLIDE ボリード」である。
1920年ごろ誕生したこのモデルは、自動車で移動する際に使用するという想定でデザインされたバッグ。当時の道路は現在のように舗装されていることもなく、都市部であればデコボコの馬車道であることも多かった。そのため、振動でバッグの中身が飛び出すことも多かったという。それを防ぎながらベルトの開閉の手間も省くため、世界で初めて「ファスナー」がバッグに取り付けられたのだという。

世界初のファスナー搭載のバッグ〈HERMÈS エルメス〉の「BOLIDE ボリード」。
今ではバッグにファスナーが付いていることは珍しいことではない。しかし当時は、ファスナーを目にするところといえば軍用車の幌ぐらいで、貴重なものであったという。それをバッグに取り付けたのは極めて斬新なことだったのだ。
その影響を受け、かの〈CHANEL シャネル〉がスカートにファスナーを取り入れたという逸話もあるほど。このボリードの登場が、ファッション界に大きなインパクトを与えたことは想像に難くない。
〈HERMÈS エルメス〉を象徴する
「馬車と従者」。
そして「エルメスオレンジ」に
隠された秘密。
エルメスと言えば多くの人が思い浮かべるのが、鮮やかでありながら深みも感じさせるオレンジと、そこに描かれた馬車と従者かもしれない。
この現在も使われているロゴが誕生したのは、1945年。「デュックとタイガー(=四輪馬車と従者)」と呼ばれているこのモチーフに、エルメスの哲学が隠されていることはあまり知られていない。
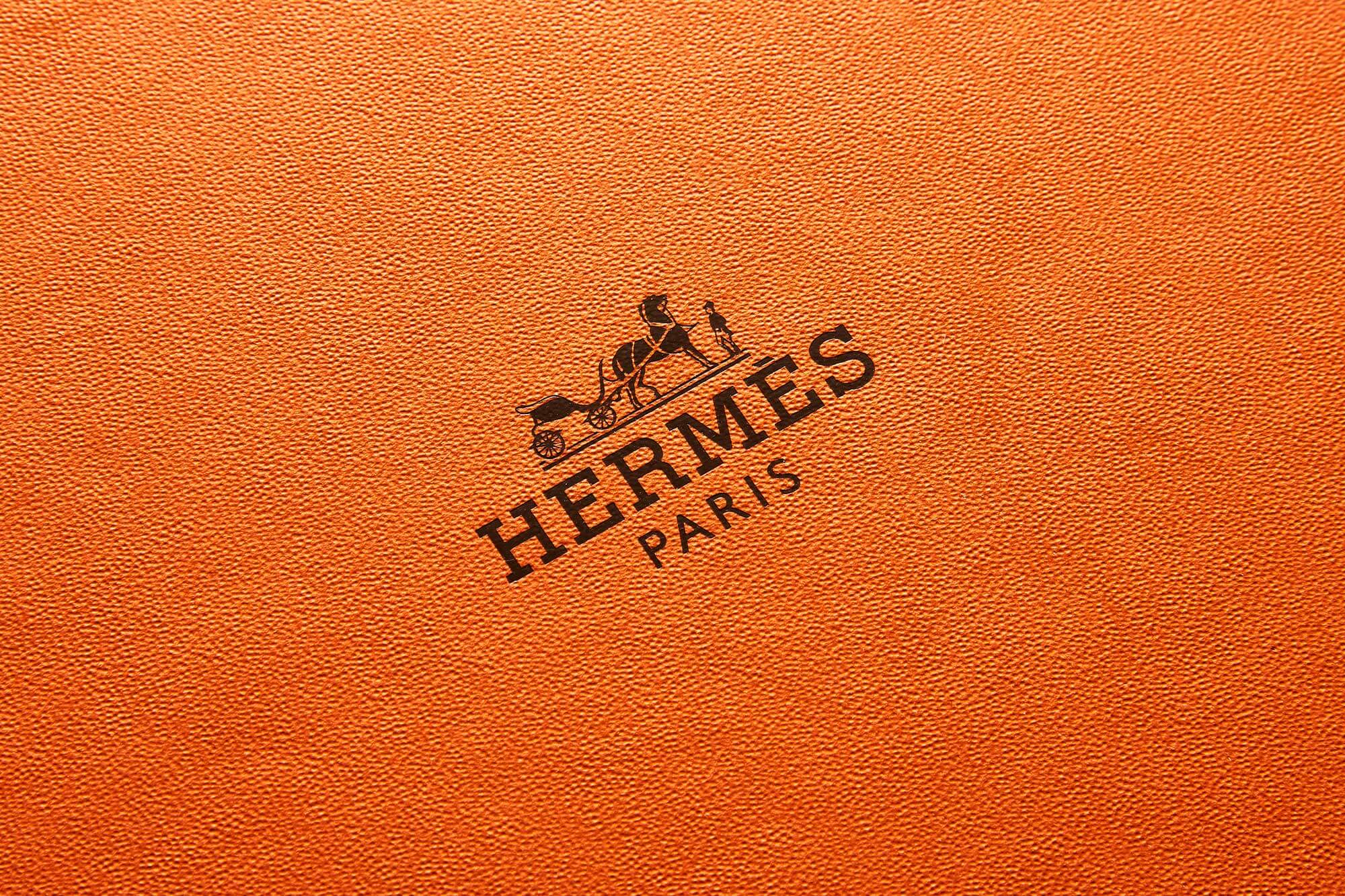
「デュックとタイガー(=四輪馬車と従者)」をモチーフにした〈HERMÈS エルメス〉のロゴ。
不思議な点にお気づきだろうか?馬車と馬、そして従者が描かれているものの、肝心の主人がそこにはいないのだ。
エルメスが創業当初から持ち続けているのが、「主役はあくまでもユーザーにある」という考え方だという。それを顕著に示しているのがこのブランドロゴなのだ。
このロゴマークでは、「従者=職人」「馬=ブランド」「馬車=ブランドアイテム」をそれぞれ表しており、「エルメスというブランドの下で職人が作り上げた、最高品質のアイテムをお客様に提供する」という構図を表しているのだという。
もうおわかりだろう。そのアイテムを使う「ユーザー=お客様」こそが、ロゴに描かれていない「主人」なのだ。
エルメスができることは、ただ最高品質のアイテムを提供するということのみ。そこに最終的な価値を見出し、享受するのは他でもないお客様自身である、という首尾一貫した姿勢。そんな哲学が、さりげなくこのロゴマークには示されているのだ。
そしてエルメスのシンボルカラーである、深みのあるオレンジ色。現在ではこのブランドに欠かせないアイコンの一つであることはご存知の通りだが、初期のエルメスの包装紙には、薄いベージュが使われていたのだという。

深みのあるオレンジ色は、〈HERMÈS エルメス〉のシンボルカラー。
それがオレンジへと変わったきっかけは、第二次世界大戦だった。大戦中の物資の欠乏によりベージュの包装紙を手に入れることが叶わず、偶然残っていたオレンジ色の紙を包装紙として使用したことに端を発しているのだとか。このオレンジの色が顧客の評判を呼び、のちにエルメスのシンボルカラーとして正式採用されることとなったのだと伝えられている。
〈HERMÈS エルメス〉のアイコン
「BIRKIN バーキン」は、
偶然の積み重ねで生まれた。
冒頭でも述べたように、エルメスのバッグの中でも群を抜いて希少性の高いアイテムが「BIRKIN バーキン」だ。

〈HERMÈS エルメス〉のアイコンともいうべき「BIRKIN バーキン」。
このバッグが誕生したのは1984年。それは、当時のエルメス社長であったジャン=ルイ・デュ マが、飛行機の席でひとりの美しい女性と隣合わせたことがきっかけだったという。
彼女は、通路を通る際よろめいてしまい、愛用のかごバッグからその中身を落としてしまったという。それを見たジャンが「ポケットがついているバッグがいいですよ」とアドバイスすると、なんと彼女はジャンの存在を知ってか知らずか「エルメスがそんなバッグを作ってくれたらいいんですけど」と答えたという。ジャンはその身分を明かすと、機内のエチケット袋に前述の「オータクロア」をベースにしながら、彼女の理想とするバッグのデザインスケッチを描いた。そして後日彼女のためにそのバッグを制作し、贈ったのだという。

偶然の積み重ねで生まれた〈HERMÈS エルメス〉の「BIRKIN バーキン」は、世の女性の永遠の憧れ。
そのシンガーの名前は、ジェーン・バーキン。そう、セルジュ・ゲンズブールや、ジャック・ド ワイヨンといった世界を代表する洒落者を虜にするとともに、永遠のファッションアイコンとして知られる世界的女優にしてシンガーだ。そんな彼女の愛用品として、そのデザインは「バーキン」と呼ばれることとなり、世の女性たちの憧れの的となったのである。
商業的に成功しながらも、
絶版となったキャンバス地のアイテム。
1998年、ファッション愛好家の間で話題となった出来事といえば、マルタン・マルジェラが、エルメスのレディース部門のクリエイティブディレクターに就任したことだろう。

マルタン・マルジェラ時代の〈HERMÈS エルメス〉のカジュアルラインの「FOURRE-TOUT フールトゥ」(左)と「HER LINE エールライン」(右)。
そして同年、エルメスは一世を風靡するアイテムを発表することとなる。カジュアルラインの「FOURRE-TOUT フールトゥ」と「HER LINE エールライン」だ。オールキャンバス地でカジュアルにも合わせやすいと同時に、エルメスのラインナップの中では比較的購入しやすいということも相まって、定番としてその後も根強い人気を誇っていた。
しかしこの二つのモデルは、2006年に突然の製造を終了。その後、その後継とも言われる、カジュアルでありながら部分的にレザーが使われた「Acapulco アカプルコ」と「Valparaiso バルパライソ」が誕生した。この変遷から、エルメスの革製品に対する想いやプライドを感じることもできるだろう。
〈HERMÈS エルメス〉が
人々を魅了してやまない秘密とは。
エルメスの製品は、すべて職人の手によって生み出されている。しかも、ひとつの製品の製造工程すべてを、ひとりの職人が仕上げるのだ。
バーキンのみならずエルメスの製品の多くには、職人ナンバーやアトリエを表す英数字、製造年が刻印されており、いつ・どこで・どの職人がつくったのかが分かるようになっている。

〈HERMÈS エルメス〉製品のベルト部分の刻印。
これはブランドとしての誇りの表れであり、エルメス社が職人たちに向けた敬意の表れであるともいえよう。
エルメスの革製品を直営店へと修理に持ち込むと、その刻印が辿られ、基本的には製造を手掛けた職人自身の手で修理が施されるのだという。このようなアフターケアの姿勢は、ユーザーに安心と信頼を与えるとともに、エルメスというブランドと製品に対する深い愛着をも生むことに繋がる。
一方で、職人にとっても、ユーザーに愛用された製品を再び自らの手で補修することはこの上ない喜びであろう。それは修理してまで同じ製品を愛用し続けたいという、ユーザーの気持ちの表れに他ならないからだ。そしてそうした思いをさらに確かなものにするために、エルメスはより良いプロダクトやサービスを提供し続けてゆく。

ため息が出るほど美しい〈HERMÈS エルメス〉の革製品。
エルメスの製品は、決して安いものではない。
もちろんそれは、厳選された高品質の素材を使い、熟練した職人の手により、一切の妥協なく製造されることを考えれば、極めて妥当な価格とも思える。
だが、それと同時に下記のようなことも言えるのではないだろうか。
徹底したアフターケアまで含め、エルメスの製品は永く使い続けられる、言葉通りの「一生モノ」であるという自信のあらわれなのだと。
バーキンは、高額であるのはもちろんだが、その希少性から、ただ金を積めば手に入るという類のアイテムではなく、万人が手にできるものでもない。それでも世の女性たちがバーキンに恋い焦がれるのは、やはりそれが人生において、誰もが一度は手に入れたいと思える一生モノだからではないだろうか。
高い技術を持つ職人が作り上げたアイテム。それがお客様の手へと届けられ、お客様自身の要望に応じていつでも同じ職人が補修を行うという、製品を通したユーザーとブランドとの密な繋がり方は、世のラグジュアリーブランドの中でもエルメス特有のものといえるだろう。
そしてそれゆえ、エルメスは圧倒的に格上のブランドとして認知されているのではないだろうか。

先に述べたエルメスのブランドロゴを思い出してほしい。
エルメスとその職人(=馬と従者)は、ひたむきに最高の製品(=四輪馬車)を提供するのみ。馬車に乗りその最終的な価値を見出し、享受するのはお客様自身(=主人)である、 主人であるユーザーに永く愛される最高の製品をつくり続けるというこの「デュックとタイガー」のモチーフに込められた経営哲学にこそ、エルメスがいつの時代も人々を魅了してやまない理由といえるのではないだろうか。