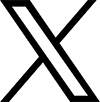京都紋付によるリウェアプロジェクト「K」〜黒の再生〜【前編】
この『knowbrand magazine』では、これまで1つのブランドやファッションアイテムにスポットを当てて、その背景にある物語とともにプロダクトの魅力と価値を伝えてきた。なかでも日本から世界中のモードシーンに影響を与え続けてきたブランド〈COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン〉の魅力に迫った記事は、これまで以上に多くの反応が得られた。
固定観念に囚われない“自由”な発想や、ブレず貫き通してきたクリエイションとその姿勢の源にある“黒”への敬意の念を込めて、「黒の自由」と題した同記事。その文中でも触れたが、ギャルソンは1982年にパリで行われたショーにおいて、全身を黒一色で覆ったコレクションを発表。モード界では死や反抗を意味することからタブー視されていた黒を用いることで、旧来の美意識の前に衣服の新たな解釈や可能性、いわばファッションの自由な表現や捉え方を突きつけた。そう、黒に新たな価値を見出したのである。
以降、ファッション界は最も洗練された色として黒を享受し、今や社会的常識となった。そして不景気が叫ばれる現在における黒は、コンサバティブの象徴として認識されている。ファッショントレンドと社会情勢の因果関係の話がある。好景気下では、華美なモノが求められて大量消費されるが、反対に不景気下では、ベーシックで長く使えるようなモノが求められる…というもの。このベーシックで長く使えるモノの代名詞が“黒”。人々はいま“黒”を求めているのである。
和の伝統が生んだ“ヨウの美”
死の象徴を再生のキーカラーに。

さて、序文において死を表すと述べた“黒”。この色に新たな価値を見出した企業が京都に存在する。日本の伝統的な正装である「黒紋付」を100年以上染め続けてきた〈京都紋付〉である。その歴史の始まりは1915年(大正4年)。初代・荒川金之介により、荒川染工場として現在の地に創業。1969年に2代目が株式会社〈京都紋付〉を設立し、画期的な濃色染め“純黒”を考案。1989年には昭和天皇大嘗際における装束「小忌染」を再現製作し、業界内で確固たる地位を築く。そして現在。4代目社長・荒川 徹氏のもと、紋付の染色だけでなく、革新的黒染め技術“深黒(しんくろ)”を用いて、国内外のアパレルブランドの黒染め加工を請け負うように。
2013年には、WWFジャパンとコラボレーションを行い、本格的に衣類を黒く染めて再生する事業、PANDA BLACKプロジェクトをスタート(※現在はサービスを終了)。同時に一般消費者から染め替えの受注オーダーを始める。この新たな取り組みは2020年から「K」プロジェクトとして、さらに活性化し染め替えをデザインとして提案する事業に発展。今では、サステイナブル観点から、廃棄衣料削減の環境問題解決にも取り組んでいる。こうして日本が誇る伝統技術による“和の黒”は現代において、再生のキーカラーとなった。
では、その黒を生み出す“黒染”とはどんな技術なのだろうか?更なる黒の可能性を探るべく、我々は京都紋付の所在地である古都・京都へ向かった。
京都で100年間受け継がれてきた技術
黒にこだわり、黒に生きる。


訪れたのは、京都駅からもそう遠くない京都市中京区壬生松原町。細い路地を抜ければ、丹精込めて育てられた花々の鉢植えが並ぶ民家や、歴史を感じさせる木造建築の町屋などがある。いわゆる京都らしい街の一角。近隣には、あの新撰組が屯所としたことで有名な壬生寺や八木亭もある。この地に日本の黒染業界のパイオニア・京都紋付はある。


ここでは代々続く生業である黒紋付の染色と、新たに行われている洋服の染め替えが行われている。
せっかくの機会なので、黒紋付とはどういったモノなのかを改めて説明しておこう。現在、約2万種類あるという家紋。自らの家系、血統、家柄・地位といった出自を示す、この日本固有のシンボルが入った黒紋付は、相撲取りや歌舞伎役者などの伝統芸能の衣装のほか、葬式の喪主や結婚式の新郎が着用する正装(第一礼装)として、我が国の文化の中に溶け込んでいた。

だが、この黒という色は厄介で、深みのある色合いを表現するのが非常に困難。ゆえに従来の技術では、何度も下染めを繰り返して色を重ねていく必要があり、黒紋付は手間がかかった非常に高価なものであった。これを京都紋付では長年の経験と勘をデータに置き換え、反応染料と独自技術でどこよりも“深く黒い”黒染を実現。この技術を応用して、着込んでいく内に褪色したり汚れがついてしまったりして着なくなった洋服を、黒く染め替えることで生まれ変わらせる。これが京都紋付の染め替えである。
ではここからは、実際に染め替えの工程を追っていこう。
実際の染め替えとはどういうものか
染料の計量〜室内干しまで。


まずは染め替えする衣類の総重量に合わせて、黒の染料を計量するところから。ここで使われるのは反応染料と呼ばれるもの。主に綿や麻、レーヨン、シルクなどを染める際に用いられ、繊維と化学結合して染着するので耐久性に優れているのが特徴。これにお湯を加えて攪拌しながら溶かして染料を作る。


全国から集まってきた染め替え希望の衣類を、まとめてドラム式染色機に入れていく。ちなみに一度に25kgまで投入可能。続いてドラムに水を貯め、助剤(アルカリ性で、これを入れることで生地が染まりやすくなる)を入れて60℃になるまで25分ほどドラムを回して、よく馴染ませる。


助剤がしっかり馴染んだら、染色機に染料を投入し約3時間かけて機械を回しながら染色していく。先述の通り、京都紋付では染めをデータ化しているが、季節や気圧の変化も影響してくるため、ムラなく染めるには職人の手による微調整も必要。時間が経ったら、染色機内に溜まった染料を排出する。


水洗いののち、ソーピング剤を加えて生地に定着しなかった染料を洗い落とす作業に移行。洗いが終わったら遠心脱水機に投入し、衣類に残った水分を一気に脱水。この時点ではまだ濡れているため色濃く見えるが、実際にどれくらい染まったかは乾いてのお楽しみ。


染め上がった衣類は、建物内の運搬用エレベーターを使って、階上の干し場へと持ち込まれる。ここで1点ずつ確認しながら、手作業で室内干しされる。このあとにはまだ、更に黒くするための重要な工程「深黒加工」が残っているのだが、外部に公開されているのはここまで。

和の伝統技法“黒染”を継承し、現代にフィットした進化の道を歩む京都紋付。
この【前編】では、日本から世界へ黒の新たな価値を問いかけ、黒という色に秘められた可能性を提示する同社を訪れ、実際の染め替え工程を追いながら、100年以上の歴史を持つ老舗が誇る高い技術力と飽くなき探究心の一端に触れた。
続く【後編】では、実際に我々が持ち込んだ衣類を染め替えした結果、どうなったのか。Before & Afterで黒を追求する京都紋付の真価をお見せする。