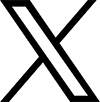ナイキのキセキ。【vol.02】
むしろ「スニーカー」というファッション要素の強い呼称の方が耳慣れている昨今、着用されるシーンは陸上用トラックや球技のコートより、圧倒的に日常のストリートなのである。
ところで、人が三人寄れば派閥が形成されるという。〈converse コンバース〉、〈adidas アディダス〉、〈Reebok リーボック〉、〈PUMA プーマ〉、〈VANS ヴァンズ〉そしてナイキ。それ以外にも現代にスニーカーブランドは多く存在するが、果たしてあなたは、何派であろうか。
きっと最大派閥となるのは、ナイキだろう。群を抜いた機能性や先駆的なデザインはもちろん、〈AIR JORDAN エア ジョーダン〉をはじめとした他を圧倒する魅力的なシリーズの数々で、常に我々を魅了してやまないからだ。
中でも多くの人にとっても馴染みのあるプロダクトネームが「AIR MAX エアマックス」ではないだろうか。ナイキの軌跡の中で、最も画期的にしてセンセーショナル、かつ最大のムーブメントを起こした奇跡のシリーズである。
我々を惹き付けつづけるナイキの「軌跡」を追う特集の第二弾は、エアマックスシリーズから始めてみるとしよう。
エア マックスのキセキ。
1978年、〈NIKE ナイキ〉が「AIR TAILWIND エアテイルウィンド」に採用した「エア」を搭載するクッショニングシステムは、ランニングシューズはもとより、1985年登場の「AIR JORDAN 1 エア ジョーダン 1」にも採用され、ナイキはもとよりスポーツシューズ業界そのものの新時代を切り拓くこととなった。
だが両モデルともソール部分のルックスは地味なものであり、当時はエアの持つクッション性能のスペックは、履いたユーザーにしか伝わっていなかった。よってナイキの次なる課題は、機能面でもコンセプト面でも優れたエアテクノロジーを効果的かつインパクトをともなってユーザーに訴えかけるデザインを具現化することであった。
そのミッションに挑んだのが、のちに伝説のデザイナーと称され、シリーズ3作目からエア ジョーダンのデザインも担当することになるティンカー・ハットフィールドである。そして彼がパリで訪れたポンピドゥー国立芸術文化センターに着想を得て、デザインしたのが「最大」のエア容量を搭載し、1987年に発表した「AIR MAX 1 エア マックス 1」であった。
その最たる特徴は、外から内部が見えるポンピドゥー国立芸術文化センターの構造を見事にデザインに落とし込んだソールだ。従来よりも大型化したエアバッグがミッドソール側面から大胆に覗く「ビジブルエア」である。

世界初のエアバッグが見えるデザイン「ビジブルエア」を採用した「AIR MAX 1」
ナイキだけがもつエアテクノロジーを「可視化する」というかつてない衝撃的なデザインは、それそのものが認知拡大のための最大のプロモーションとなり、ユーザーの心に刺さることになる。ファーストモデルの成功を受け、エアマックスは年を追うごとにエアのボリュームを増大させ、デザインも進化させてゆく。「ハイテクノロジー」時代のはじまりである。
そして1995年夏、社会を揺るがすことになる奇跡の「ハイテク」モデルがローンチされた。「AIR MAX 95 エア マックス 95」だ。
ファッション、スニーカーへの興味の有無にかかわらず、もはや説明不要といえるほどにまで多くの人々に知れ渡っているモデルであろう。このモデルをめぐる異常なまでのフィーバーは、度を越えた価格の高騰、フェイク品の流通、ひいては「エア マックス狩り」と称される強奪事件を巻き起こすまでに至った。

「AIR MAX 95」(1995)。通称「イエローグラデ」。シリーズ初の前後ビジブルエア化を実現したエポックメイキングモデル
なぜそれほど人々を熱狂させたのか。その理由は定かではない。むしろ発売前は、そのあまりに斬新なデザインゆえ、高セールスは期待されておらず、流通量もさほど多くはなかった。ほどなくして一部の高感度なファッショニスタたちの琴線にふれたのを機に人気に火が灯り、瞬く間に飛び火。だがそもそもの流通量の少なさから国内正規販売分はすぐに枯渇化してしまったという流れはあっただろう。
手に入らないとなれば、欲しくなるのが道理。とてつもなく膨れ上がったニーズは、常軌を逸したマーケットを形成してゆく。ファッション誌による「ハイテクスニーカー」の煽り記事も手伝い、エア マックス 95をめぐる狂騒劇はブームという域を超え、社会現象または社会問題といわれるまでになったのだ。
だが一方で、日本で起こったこのムーブメントが、老若男女を問わず本来アスリートのためのハイテクスニーカーで「オシャレする」という行動・文化を普遍的なものにしたことは間違い。さらにその流れは世界にも波及し、熱烈なコレクターであるスニーカーヘッズを多く育むことになる。ナイキのスポーツシューズはもはや走るための高性能な道具という枠には収まりきらない、所有するだけでも価値のある存在となったのだ。

1:「AIR MAX 1」(1987)
2:「AIR MAX 90」(1990)。エア マックスの3rdモデル
3:「AIR MAX BW」(1991)。より洗練された4thモデル。BWは「ビッグウィンドウ」の略で、それまでうよりエアが覗く窓が大型化
4:「AIR 180」(1991)。エアマックスシリーズではないが、従来よりも大幅にエア容量の増大に成功したモデル
5:「AIR MAX 93」(1993)。さらにエアの容量をアップし270度のビジブル化を果たす
6:「AIR MAX 95」(1995)
7:「AIR MAX 96」(1996)。前年の95から大幅なイメージチェンジが施された
ウラハラのキセキ。
1990年代初頭のビンテージ衣料に新たな価値を見出すという流れと同じく、エア マックス95に代表されるスニーカーブームは明らかに日本が発端となった。よってファッショントレンドにおいて、日本の動向は世界中から注目され、その影響力の大きさは計り知れなくなってゆく。
そして東京は原宿の裏通りで同時多発的に生まれた数多のブランドを発信源とした熱狂的なムーブメント、俗にいう「裏原ブーム」もまたしかりである。その始まりは、1993年。いまや世界的なブランドとして人気を博す〈UNDERCOVER アンダー カバー〉〈A BATHING APE ア ベイシング エイプ〉を初めて展開した「NOWHERE ノーウェア」という小さなショップであった。各々のブランドを立ち上げた高橋盾とNIGO®の才能もさることながら、そこにはやはり当時すでに独自の嗅覚と審美眼でファションシーンにインパクトを与え続けていた稀代のクリエイター、藤原ヒロシの存在が大きかったといえる。本人が望むと望まざるとに関わらず、裏原ブームは彼の存在なくしては起こらなかったのだ。
(→〈UNDERCOVER〉に関連する特集記事はこちら)
(→〈A BATHING APE〉に関連する特集記事はこちら)
藤原ヒロシという人物の肩書はなにか。日本におけるDJのパイオニアにして、プロデューサー、ミュージシャン、デザイナー、ディレクター等々。もはや肩書など彼の前では意味をなさず、洋の東西、規模の大小を問わずに様々なフィールドを軽々飛び越え、飄々と活躍するミステリアスな存在だ。いささか月並みで散々使い古されてはいるが、やはり「カリスマ」という表現がもっともしっくりくるだろう。〈STUSSY ステューシー〉をはじめとしたストリートブランド、またはストリートカルチャーという概念そのものを日本に紹介し、価値あるものとして浸透させた張本人でもある。
当時すでに絶大な影響力をもっていた藤原ヒロシのセレクトするアイテムは、雑誌での自身の連載記事で紹介されるやいなや争奪戦が繰り広げられていた。その中には当然、ナイキのスニーカーもあった。エア マックス95の余波もあり、世はスニーカーブーム。新モデルや新色の情報に多くの人々が胸を躍らせていた。中でも藤原ヒロシがチョイスするアイテムは、フォロワーたちのハートを鷲掴みした。いわば最高のセンスの化身ともいえる藤原ヒロシの「お墨付き」を手に入れることは、当時の若者たちの最重要ミッションだったのだ。
くしくもエア マックス95 と同時期の1995年にデリバリーされた「AIR FOOTSCAPE」もまた彼に紹介されたモデルだ。そもそもシューレースが斜めに配置されるアシンメトリーなデザインと幅広のフォルムだけでも従来のスニーカーの概念を覆したわけだが、そこに藤原ヒロシのお墨付きである。当然、日本では枯渇化した。

「AIR FOOTSCAPE」(1995)。人間工学に基づいたデザインは、当時大きな衝撃を与えた。
エア マックス自体のブームは、落ち着きを見せつつあったが、ナイキ自体はあくまでスポーツブランドとしてのスタンスを崩すことはなく、たゆみなく革新的なアプローチを模索し続けていた。最先端で革新的なデザインを目指し1999年に始まった「ALPHA PROJECT アルファプロジェクト」もその一端であり、2000年に登場した「AIR ZOOM SEISMIC エア ズーム サイズミック」や「AIR KUKINI エアクキニ」「AIR PRESTO エア プレスト」は、いずれもセンセーショナルなモデルであった。

「AIR PREST」(2000)。XS/S/M/L/XLというトップス衣料的サイズ展開が話題になり、ルックスの良さからタウンユースでも大人気となった
また、かねてよりストリートで絶大な支持を集めていた不朽の名作「AIR FORCE 1 エア フォース1」は、様々なカラーバリエーションで提案され人気を博していた。特に2001年リリースの通称「白蛇」「黒蛇」と呼ばれたモデルは、正規価格の販売分は瞬く間にショップから消滅。「白蛇」にいたっては、NIGO®が愛用モデルとして紹介したこともあり特に価格が高騰した。

1:「AIR FORCE 1 HI」(1982)。ナイキのバスケットボールシューズのスタンダード
2:「AIR FOOTSCAPE」(1995)。
3:「AIR MAX 97」(1997)。エアバッグが初めてソール全体へと拡大されたフルレングスビジブルエアを搭載
4:「AIR MAX 98」(1998)。配色が似ていることから通称「ガンダム」と呼ばれている
5:「AIR ZOOM SEISMIC」(2000)。「アルファプロジェクト」からのモデル。アグレッシブなルックスが話題となった
6:「AIR PRESTO」(2000)。
7:「AIR KUKINI」(2000)。「アルファプロジェクト」からのモデル。シューレースを排したチャレンジングなデザイン
8:「AIR FORCE1 LOW」(2001)。通称「白蛇」。
9:「AIR FORCE1 LOW」(2001)。通称「黒蛇」。
リバイバルのキセキ。
ハイテクスニーカーブーム、裏原ブームの時代、ナイキのシューズだけをみても幾多の興味深い物語が存在する。きっとそれは世の熱い視線が常にスニーカーを筆頭としたファッションにフォーカスされていたがゆえに目立ち、記憶・記録されやすかったからでもあるだろう。
たとえば1996年。NBAの異端児デニス・ロッドマンの着用予定モデルとして華々しく登場した「AIR BAKIN エア ベイキン」は、思わぬ逸話を残している。毒々しいルックスで発売前から話題となっていたのだが、ヒールの炎をあしらった「Air」の文字がイスラム教の唯一神「Allah アッラー」に見えるとの批判から、発売後間もなくして約38,000足を回収する騒動となったのだ。

炎を模したヒールの「Air」の書体が物議を巻き起こした「AIR BAKIN」(1996)のオリジナル。劣化(加水分解)したソールが本物の風格
スニーカーを日本中が追い求めた微熱を帯びたようなあの時代の中心に、間違いなくナイキがあった。日本社会にとっては後にも先にもない実に特異な時代として、ナイキにとってはテクノロジーの大幅な進化を遂げた時代として語り継がれるはずだ。事実、近年90’sリバイバルと呼ばれるムーブメントも話題となった。1990年代を彩ったスニーカーの再販は、当時を知る者のノスタルジーを掻き立て、当時を知る由もない若者たちには極めて新鮮に映ったのだ。

1:「AIR MORE UPTEMPO」(1996)。AIRの文字そのものがデザインとなった大胆なサイドビューで話題沸騰となったモデル
2:「AIR MAX PLUS」(1998)。アメリカのスポーツチェーン大手「FOOT LOCKER」の専売モデルとして登場後、定番化した人気モデル。
さらに裏原ブームには、ブランド同士のコラボレーションやWネーム、別注モデルの製作という流れ、または文化を一般化したという大きな功績もある。藤原ヒロシにいたっては、ナイキのデザイナーであるティンカー・ハットフィールドとCEOのマーク・パーカーとの究極のコラボレーションともいえる「HTM」という実験的プロジェクトに参加し、数々のユニークなモデルを発表、当然争奪戦が繰り広げられた。近年でもナイキとのコラボレーションは多く誕生しているが、ここでも1990年代後半から2000年代初頭のリバイバルモデルが目立つことに驚きだ。

1:「HTM AIR WOVEN」(2002)。藤原ヒロシ、ナイキのティンカー・ハットフィールドとマークパーカーの頭文字をとった「HTM」から生まれた傑作。
2:「AIR JORDAN Ⅴ」×〈Supreme〉(2015)。1990年の傑作エア ジョーダンⅤをシュプリームがチョイスして話題になった
3:「AIR PRESTO」×〈BEAMS〉(2016)。ビームスの40周年を記念したモデル。2000年のエアプレストがベース
4:「AIR MORE UPTEMPO」×〈Supreme〉(2017)。1996年のモア アップテンポをベースに「AIR」の文字を「SUPREME」に大胆アレンジ
5:「AIR MAX 95」×〈ATMOS〉(2018)。日本のスニーカーセレクトショップであるアトモス提案のモデル
個性際立つかつてのモデルがいまだに評価され人気を博している事実に、ナイキのつくり出すプロダクトの完成度の高さを改めて感じずにはいられない。しかしナイキは過去のアーカイブへのリスペクトはしつつも、決して立ち止まったりはしない。

“THERE IS NO FINISH LINE(終わりはない)”
かつてナイキの標語となっていた言葉だ。その言葉通り、過去の爆発的なヒットモデルに甘んじることなく、さらに我々を驚愕させる奇跡のような革新的モデルを次々に生み出してゆくことになる。