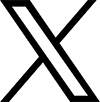ワールドクラス・ジャパン“セカイに誇るニッポンのモノ”〜〈オアスロウ〉編〜
このたび取り上げるのは、ファストファッション的なジャパンブランドとは真逆の、ある種“スロウ”なニッポンのモノ。趣深くタイムレスな、オーセンティックなアイテム群。いざ、リアルジャパニーズクローズ〈orSlow オアスロウ〉の領域へ。
ヴィンテージを知り尽くす男が
辿り着いた、
これからのスタンダードウェア。
オリジナリティ(originality)のある服を吟味し、自らのフィルターを通してスロウ(slow)にデザインしていく。そんなコンセプトをそのまま名前に冠した〈orSlow オアスロウ〉は2005年に生まれた。デザイナーは仲津一郎。ブランドとしての発端は、なんと彼が6歳の時にまで遡るという。当時、母親に買ってもらったデニムのオーバーオール。その独特な素材感に感銘を受けた仲津は、以降アメカジの、そしてヴィンテージウェアの沼にハマっていく。
地元・大阪の古着街はおろか、高校卒業直後には本場アメリカの古着ショップにまで通い詰め、帰国後は独学でオリジナルジーンズを製作。服飾学校を経て、ジャパンデニムの中心地である岡山県・児島の老舗ジーンズメーカーに約5年間籍を置いた。そして独立後、2004年に立ち上げた〈slowdenim スロウデニム〉を前身としてオアスロウをスタートさせる。
現在も企画・パターン作成の全てが自社アトリエにて行われるが、そこには1960年代のアメリカ製ミシン「ユニオンスペシャル」、50年代に使用されたシンガー社のミシンといった希少機をはじめ、20台もの織機が並ぶ。オリジナルに多大な敬意を持ち、ゆっくりと前進する。ブランドの真髄と見事にリンクする、仲津の実直な歩み。だからこそオアスロウのプロダクトは、まるで丁寧に紡がれた糸のような必然の美を放つのだ。
「US ARMY FATIGUE PANTS STANDARD
USアーミーファティーグパンツ
スタンダード」
ブランド黎明期から続く、
アメリカンワークウェアの新解釈。
さて、ここらからはゆっくりと傑作をご覧いただくことにしよう。「US ARMY FATIGUE PANTS STANDARD USアーミーファティーグパンツスタンダード」は、ブランド黎明期の2006年より継続する人気アイテム。ご存知アメリカ軍用の作業服がモチーフで、日本ではなぜか「ベイカー(=パン職人の)パンツ」とも呼ばれるデザインである。
(→「ベイカーパンツ」に関連する別の特集記事は、こちら)

アメリカ軍用のワークウェアを源流とする「US ARMY FATIGUE PANTS STANDARD USアーミーファティーグパンツスタンダード」。


フロントはボタンフライ。バックには大ぶりのポケットを備え、背面ウエスト部にアジャスターが付く。
オアスロウのファティーグパンツはこれまでに何度かのマイナーチェンジを繰り返しているが、いずれも1940年代に生まれたUSアーミーの“初期型”と呼ばれるモデルがベースになっている。ボタンフライのフロント、アジャスターボタンの付属したウエスト部などを備え、特徴的な大きなフロントポケット、バックのフラップポケットとともにアイコニックなビジュアルを構築した。
素材にはオリジナルで手掛けたコットンのムラ糸を使い、凹凸が横縞のように表出するバックサテン地に。ゆえに、繰り返し着用することで高品質のデニムに劣らない経年良化が楽しめるのだ。シルエットはややワイドかつ自然なテーパード。なお、同素材・同デザインの細身タイプ「SLIM FIT スリムフィット」も存在する。
「105 STANDARD
105 スタンダード」
時代に流されず、逆らわない。
定番の5ポケット。
デザイナーである仲津の経歴からも明らかなように、オアスロウの数多いラインアップの中でもデニムは特別な存在だ。とりわけ「105 STANDARD 105 スタンダード」はブランド発足3年後の2008年に登場して以降、定番中の定番として君臨するストレートシルエットの5ポケットである。

ブランド発足以降、約3年の歳月をかけて理想を追求した「105 STANDARD 105 スタンダード」。
特別なムラ糸を旧式のシャトル織機で織り上げた13.7オンスのデニムは、ヴィンテージさながらの質実剛健な佇まいが特長。それでいて、デザイナーの目指す「私生活で着て苦痛にならず、長く愛着を持って着られるワークウェア」という理想が体現されている。タフネスだけでなく、美しいシルエットや快適な着心地に細心の注意を払うことで、日本製デニムを新たな領域へと引き上げたのだ。


ボタンフライやセルビッジといった渾身のディテールからも、名品の空気感が放たれる。
ボタンフライやセルビッジなど、ディテールから放たれる空気感はまさしく名作のそれで、一説によると1950年代後半~60年代の〈LEVI’S リーバイス〉の「501XX」がベースとなっているとも。となればリジッドの状態もさることながら、デニムラバーであればやはり経年変化が気になるところであろう。

タグにもデザイナーのこだわりが。ジャパンメイドの矜持を示す日本地図の横には、仲津自らがマウスで描いたロゴが。
と、その前に。デニムに対して並々ならぬこだわりを見せるジャパンブランドの、細部に秘めた矜持をもう少々紹介したい。ウエスト内側に配されたタグには日本の地図とともにブランド名が乗せられるが、この文字はデザイナー自身がマウスで描いたものだという。古き佳きデニムと向き合いながら、新たな技術・服作りへも意欲を向ける。タグひとつからも、オアスロウのあり方がしっかりと感じ取れるのだ。

味のあるエイジングは圧巻。リユースマーケットで自分好みを探すのも一興だ。
閑話休題。では、色落ちの進んだモデルのご紹介といこう。ご覧の通り、ヒゲやハチノスがしっかりと刻まれたインディゴは、もはや芸術の域。育てるほど風合いを増すオアスロウのデニムは、長年履き続けることで真価を発揮するとも言える。ただし、リユースマーケットであれば様々な状態のデニムが眠っており、自分好みの1本を探す大いなる助けとなるだろう。
ちなみに、105と同じデニム生地を使いつつテーパードを効かせた細身の「107 IVY FIT」も根強いファンを獲得。こちらはより上品な印象で、“アイビー”の名に恥じずシャツやジャケットスタイルにハマってくれる。
「40’S OVER ALL
40’sオーバーオール」
レトロかつアイコニックな
ブランドの顔。
お次はデニム地のオーバーオール。感のいい読者ならすでにお気付きかもしれないが、前述したブランド発足のきっかけとなったアイテムに想いを馳せた「40’S OVER ALL 40’sオーバーオール」だ。とはいえ、デザイン的なベースとなったのは、仲津の幼少期よりさらに時を遡った1940年代の1着。少年時代に見た数々のアメリカ映画からも影響を受けたというデザイナーの原体験が、このレトロなオーバーオールに詰まっているという見方もできそうだ。

「40’S OVER ALL 40’sオーバーオール」は、ブランドの背景を知ればどこかノスタルジックにも映る。
2008年にリリースされてから、基本的な作りは変わらず。オリジナルの9オンスデニム生地を用いたワイドシルエットで、機能的なディテールも充実している。胸部分にはフラップ付きのポケットと、ペンホルダーを備えたウォッチポケットを配置。左右にはツールポケットとハンマーポケットを設け、アメリカンワークの王道を謳歌する。


アシンメトリーなフロントポケットをはじめ、三本ステッチやドーナツボタンなど細部にまでこだわりが満載。
各所にあしらわれたドーナツボタンからは、ヴィンテージウェアへのリスペクトが香る。物資不足に悩まされた第二次世界大戦時の月桂樹デザインを踏襲し、さらにエイジングを表現すべく錆加工まで施すという熱の入れよう。他にも、ショルダーストラップのアジャスターに某有名ワークウェアの意匠を再現するなど、とことんマニアックな姿勢には驚きを禁じ得ない。
「50’S COVER ALL
50’sカバーオール」
性別を問わず頼りたい、
武骨でキュートな出で立ち。
デニム製の羽織りものとしては、2008年デビューの「50’S COVER ALL 50’sカバーオール」を推したい。「40’sオーバーオール」同様に9オンスと比較的軽く、ラグランスリーブが動きやすさも担保。秋口から早々に活躍が期待できそうだ。

ラグランスリーブ&Aラインシルエットが着こなしの幅を広げる「50’S COVER ALL 50’sカバーオール」。
こちらは大戦後の1950年代に作られたアイテムからインスピレーションを得ており、ゆったりとしたAラインシルエットにワークウェアらしい三本ステッチがアクセントを与える。胸ポケットは左右でデザインが異なり、右胸ポケットの上部にはスクエアなワンポイントステッチが施される。



各所の強固なステッチングがワークウェアの本懐を語る。ポケット裏には当て地を施し、いっそうタフな作りに。
絶妙なカーブを描く大ぶりのハンドポケットの恩恵か、全体的には武骨に見えながらも少々のキュートさを残す点がユニーク。着用者の性別を問わず、装いのキーアイテム候補となる。言わずもがな、経年変化も大いに期待したい。
「60’S DENIM JACKET
60’sデニムジャケット」
タイムレスでモダン。至極の二律背反。
最後もデニムの名品をピックアップ。2009年誕生の「60’S DENIM JACKET 60’sデニムジャケット」は、アメカジのど真ん中を射抜く正々堂々としたデザインを備える。両胸ポケットから伸びたV字型のステッチワーク、身体のラインに沿うややタイトなシルエット。リーバイスが1962年に生み出した通称“3rd”をモチーフとするのは、もはや周知の事実だ。なお、リーバイスのデニムジャケットは1stや2ndも著名だが、それらの違いについては下記の記事を参考にされたし。
(→関連する特集「オリジナルたるタイムレスな定番デニムジャケットを知る。」)

1962年に生まれた通称“3rd”をモチーフとする「60’S DENIM JACKET 60’sデニムジャケット」。
ある意味でデザイン的に完成された60年代のマスターピースに範を取りながらも、オアスロウ的なこだわりを追求する。着丈や身幅、アームの太さといった細部を一から見直すことで、日本人にとって最適なフォルムを作り上げ、真のヘビーデューティにつながる着やすさを考慮した。

両胸のポケットからは特徴的なV字型のステッチが走る。
生地は当然オリジナル。ムラ糸を使用した13.5オンスのデニムは着るほどに身体へ馴染み、風合いが深まる。嘘のないスロウな味わいが、時間の経過とともに明らかになっていくのだ。

エイジングが進んだ「60’S DENIM JACKET 60’sデニムジャケット」は、新品とはまた違った美しさを見せる。

高品質な13.5オンスのデニム地を使い、着込むほどに味わいが豊かに変化。

以上、オアスロウの真髄を代表的な5アイテムとともに振り返った。なにかと刺激がもてはやされる現代において、それは純粋すぎるほどにオーソドックスで、愚直とさえ言えるかもしれない。しかし、そんな姿勢こそが今、真に求められる本質ではないだろうか。試行錯誤の末に仲津が立ち上げ、今も少数精鋭のスタッフで紡がれるブランドは、決して嘘をつかない。
4年ぶり、いや5年ぶりに開催されたスポーツの祭典が“災”典ともなりかねないなか、これまで以上に世界中の視線を集める日本。本質を見据え、ゆっくりとニュースタンダードを作り上げるジャパンブランドは、未曾有の状況でひときわ輝いて見える。