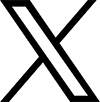ザ・ノース・フェイスが目指すファンクション×ファッションの極地【前編】
『knowbrand magazine 』の読者諸兄も、この秋冬をどんなスタイルで過ごそうかと胸躍らす日々をお過ごしのことであろう。しかし問題は、数ある選択肢の 中 から何を基準として何を選び取るべきか。その答えとして“ファンクションとファッションの両立”を挙げる洒落者たちの心を捉えて離さないのが、アウトドアブランドの創り出す高機能アウター群。
なかでもシーンの最前線を走り続ける〈THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイス〉の支持率の高さたるや。アウトドアというジャンルの枠を飛び越え、カルチャーやファッションの世界からも熱 いラブコールとリスペクトを集め続ける、その理由とは。数々の傑作を追いながら、前・後編に分けてザ・ノース・フェイスを知る。
真の機能性の追求と
自然との共存というフィロソフィー。
まずはその軌跡をクローズアップしていく。10代からアウトドアスポーツに熱中していたダグラス・トプキンスが、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコに、スキーやバックパックを取り扱うショップ〈THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイス〉を創業したのが1966年。だがブランドとしての設立は1968年。ベトナム戦争が泥沼化し、物質文明中心の社会や既存価値に対するカウンターカルチャーが隆盛を極め、鋭敏な感覚を持った若者たちは街を出て、自然へと回帰していく。その一方でアポロ8号が2度目の有人宇宙飛行と地球帰還に成功。そんな時代のことである。
ブランド名は、登山において最も征服が困難なルートを意味する“北壁=ザ・ノース・フェイス”から。アイコニックなロゴマークは、カリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園の象徴「ハーフドーム」がモチーフで、3本のラインは世界3大北壁を示す。これらは“どんなに困難にも果敢に挑戦していく”というチャレンジ精神を象徴するものだという。

THE NORTH FACEのロゴのモチーフとなったヨセミテ国立公園の「ハーフドーム」

THE NORTH FACEのロゴ
そんなチャレンジ精神を最初に形としたのが「スリーピングバッグ」。業界初の最低温度規格を表示したこの寝袋で顧客たちから厚い信頼を得ることとなり、ザ・ノース・フェイスの名は多くのアウトドアマンたちの知るところとなった。さらに大きな転機の訪れは1975年。世界初のドーム型テント「オーバルインテンション」が誕生。翌年に史上初のフレームパック「バックマジック」、さらにその翌年に「GORE-TEX® ゴアテックス®」を採用した世界初の全天候型アウトドアウェアを発表。この3年間でアウトドアメーカーとしての地位を確固たるものにした。以降もその革新の歩みは止まることを知らず、真の機能性の追求と自然との共存を目指し、アウトドアの限界点を高め続けている。
余談だが、アウトドア界の2トップとして同等の人気を博す〈patagoniaパタゴニア〉の創業者であるイヴォン・シュイナードとダグラス・トプキンスが、かつて冒険を共にした親友同士だったという話はファンなら常識。ちょっとしたトリビアとして脳裏の片隅にでも、パッキングしておいて頂きたい。
(→関連する記事は、こちら)
“マウンテン”の名前を冠した
オールラウンダー。
ひと口にアウトドアアウターと括れども、ジャンルや季節によってそのチョイスは千変万化。とはいえ諸兄が、ザ・ノース・フェイスの名から一番に思い浮かべるのは、俗にいう「マウンテンパーカ」に他ならないだろう。過酷な環境下において活躍する様々な機能と耐久性を備え、アウトドアのみならずタウンにも対応する汎用性の高さは、まさにオールラウンダー。同ブランドの魅力を知るスタートラインとして、これほど相応しいものはない。
アップデートを繰り返す、定番にして最高峰
1985年の登場以来、アウターシェルの最高峰に君臨し続けているのが「Mountain Jacket マウンテンジャケット」である。表地には150デニールの〈GORE-TEX PRODUCTS ゴアテックスプロダクト〉2層構造を、裏地には軽量で強度を兼ね備えたリップストップナイロンを採用。

「Mountain Jacket マウンテンジャケット」
さらに人間の行動科学に基づき随所にストレッチ素材を配することで、緻密なまでに計算され尽くしたシルエットと格別の着心地を実現。「ジップインジップシステム」を搭載し、ダウンやフリースなどのインナーと連結可能な点も、レイヤリングに最適と拍手を持って迎えられた。
また今季からデザインを変更。これまでにも度々アップデートを繰り返してきたが、特徴的な肩ヨークの切り替えが強調されたことでクラシック感が増し、現行モデルはマスターピースとしての存在感を強めている。

Mountain Jacketの新旧比較。 左:現行モデル 、右:旧モデル
ちなみに随所に登場するゴアテックス®だが、この素材を開発した〈ゴア社〉とザ・ノース・フェイスの蜜月関係は周知の事実。今日までに数多くの新素材を開発し、プロダクトへと投入してきたなかでも使用頻度が最も高いのがこの基本形。これだけ防水耐久性・防風透湿性を謳う素材が乱立する現在もなお“機能素材の代名詞”の称号を他に譲らないのが人気の証左といえよう。
(→関連する記事は、こちら)

信頼の証たるGORE-TEX®のロゴ
定番マウンテンジャケットを
街でライトに。
さて、そんなゴアテックス®が、信頼のブランド力と多湿な気候にマッチするという理由から日本における需要が高いというのは、読者諸兄ならご存知の通り。事実この「Mountain Light Jacket マウンテンライトジャケット」にもまた同素材が使用されている。

「Mountain Light Jacket マウンテンライトジャケット」
アイコニックな肩ヨークの切り替えなど、既視感のある外貌はマウンテンジャケットと瓜二つ。だが本作には、高い耐久性を備えた70デニールナイロンを表生地に使用するなど、細かな差異は多々。なかでも最も違いが分かりやすいのがレングス。用途の違いからくる着丈の長さはタウンユースに適しているという声も多く、その名の通りよりライトに使える一着。
ちなみに〈Supreme シュプリーム〉コラボのベースモデルとして採用されていたのは、海外限定でも復刻され、熱狂的ファンの間で話題を集めた90年代のアーカイブデザイン。時期によって変わるデザインやディテールもアウトドアウェアを知る楽しみである。
落とし込むトレンド、
極めるスタンダード。
先にも述べたようにアウトドアでは、アウターもジャンルや季節、用途によって様々な選択肢のなかから選ぶことなる。ゆえにザ・ノース・フェイスのラインアップにおいても、人気・定番のモデルは他にも数多存在し、その名を並べるにしても枚挙にいとまがない。なので、ここでは今抑えておくべき3着をピック。
約30年の時を経て復活した
前衛的カラーブロッキング。

「RAGE GTX Shell Jacket レイジ ジーティエックス シェルジャケット」
まず、今最もフレッシュなネタとして「RAGE GTX Shell Jacket レイジジーティエックスシェルジャケット」を挙げたい。90年代初頭にカウンターカルチャーとして登場したスノーボード用のウェアとして発表したモデルを、現代的スタイルに落とし込んだ「RAGE SERIES レイジシリーズ」。
大胆な配色でオリジナルを踏襲しながらも、防水透湿性に優れたゴアテックス®プロダクツの2層構造でアップデート。その先鋭的デザインは現代のストリートによくハマる。
圧倒的なまでにベーシック機能は
必要にして十分。
最新の良さがあれば、定番の良さもあって然るべき。防風性に優れた冬季のエントリーモデル「Novelty Scoop Jacket スクープジャケット」はその代表といえる。

「Novelty Scoop Jacket スクープジャケット」
マウンテンジャケット同様、インナーを連結するジップインジップシステムに対応し、表地は防水透湿性に優れた独自素材「HYVENT® ハイベント®」の2層構造。出色はなくとも余計なモノもなし。機能性は必要にして十分。
その軽妙なノリは
不測の事態にも対応する。
そのスクープジャケットとよく比較されるのが「Dot Shot Jacket ドットショットジャケット」。こちらは表地に撥水加工、裏地にも防水透湿ウレタンコーティングを施し、オールシーズンで性能を発揮。

「Dot Shot Jacket ドットショットジャケット」
防水シェルジャケットとしては軽く、コットンのような質感としなやかさを兼備。シルエットは多少短めのレングス設定でややリラックスフィット。軽く羽織れてコンパクトにも収納出来るので、ご近所から旅先まで、転ばぬ先の故として活躍する。
この2型にドライタッチのライト撥水アウター「Compact Jacket コンパクトジャケット」を加えたのが“御三家”と称されるクラシックス。ベーシックの良さを再確認するためにも、併せて覚えておきたい。
ダウンジャケットが作り上げた
ブランドの基礎
さて、ザ・ノース・フェイスを紐解いていくなら「ダウンジャケット」も忘れてはならない。そもそも冬のフィッシング用に開発され、その軽さと防寒性の高さから他のアウトドアスポーツのフィールドでも重宝されたこのアイテム。
1970年頃にはギアとして定着し、様々なデザインが誕生するのだが、ダウンパーカの原型といわれる「Sierra Parka シエラ・パーカ」がカタログに初掲載されたのは、その夜明け前である1969年。
その後、1977年度のアメリカ国内ダウンパーカ占有率の42%を、ザ・ノース・フェイス1社で占めていたというデータもあり、このことからも同ブランドの基礎を作り上げた存在はダウンジャケットである。と言って差し支えないだろう。
(→関連する記事は、こちら)
世界中の愛好家を虜にする
ノースダウンの普遍的名作。
まずは、シュプリームが定番的にコラボレーションし続けていることでも知られるロングセラーモデル「Nuptse Jacket ヌプシジャケット」に着目。デビューは1992年。当時はエクスペディション向けだった。

「Nuptse Jacket ヌプシジャケット」
2017年に制作された誕生25周年記念ショートドキュメンタリー映像では、世界中の名だたるザ・ノース・フェイス愛好家が登場。最上級クラスの700フィルパワーグースダウンによる保温性と軽量性、そしてシンプルで洗練されたシルエットを、同モデルの魅力として挙げている。
もちろんそのベストVer.である「Nuptse Vest ヌプシベスト」でも特長は継承。さらに袖をオミットしたことでレイヤリング時の有用性も向上し、ファッションアイテムとしてアプローチする人々も多い。

「Nuptse Vest ヌプシベスト」
ありそうでなかった発想
傑作ハードシェル×ダウン。
ファッション的視点で捉えるなら、防水ハードシェルの傑作であるマウンテンジャケットにダウンを封入した「Mountain Down Jacket マウンテンダウンジャケット」ほど、タウンユースに適したモデルはない。

「Mountain Down Jacket マウンテンダウンジャケット
2017年に登場するやいなや各所で即完売を記録し、その人気の高さから後に定番化。機能性も言うことなし。表地には70デニールのゴアテックス®2レイヤーを採用し、不意の雨や雪も意に介さない。要は傘いらず。
中綿に封入された600フィルパワーの光電子®ダウンは着用者自身の体温を吸収し、肌に送り返すことで自然な暖かさを持続させる。これぞブランドの根底にある“最小限のエネルギー・物質で、最大限の機能を引き出す”という思想を体現するテクノロジー。クラシカルなデザインにスペックは最新。ありそうでなかったモノを形にする。そんなザ・ノース・フェイスの挑戦心が本作には詰まっている。
超過酷なデスゾーンにも対応する
究極の断熱ギア。
ここまでにも何度か説いてきたが、挑戦心こそ同ブランドの進化を支える推進力である。世界最高齢でのエベレスト登頂を果たした三浦雄一郎が着用した「Himalayan Parka ヒマラヤンパーカ」は、デスゾーンと呼ばれる過酷な超低温下においても運動機能を損なうことなく、より安全・快適に活動することを目的に開発された。

「Himalayan Parka ヒマラヤンパーカ」 写真のモデルは旧モデル
中綿には遠赤外線効果により高い保温性を誇る「光電子®プロダウン」を、アウターシェルには「ウインドストッパーインサレーテッドシェル」がそれぞれ採用されており、汗の水蒸気は外へ透過させるが、身体の熱は逃がさないという構造もプロイクイップメントならでは。
防風&保温性能を極限まで高めて、いかなる寒冷地においても不可能を可能にする。一言で表すならば、限界に挑む探検者・挑戦者のためのウェアだ。この究極の断熱ギアにロマンを感じない男はいないに違いない。

Himalayan Parkaは、極地における最新最上級のテクノロジーを駆使して生産されるハイエンドライン「SUMMIT SERIES サミット シリーズ」に属する。
探検者たちの夢を現実に
そして不可能を可能に。
同ブランドが誇る最上位モデルついでにもう1着。前述のヒマラヤンパーカで培った技術をフィードバックさせて、強度と保温性を高次元で融合させたダウンアウターのもう一つの頂点。それが「Antarctica Parka アンタークティカパーカ」。

「Antarctica Parka アンタークティカパーカー」
最高スペックを誇るボディの左袖に誇らしげに輝くワッペンは、1989年の南極大陸横断の際に付けられていたものがモチーフ。そんなバックストーリーも冒険に憧れを抱く男心を否応なく刺激する。
先だって発表され話題になったが、今年12月には本作をベースモデルに、実現不可能といわれていた世界初の合成クモ糸繊維「QMONOS クモノス」を用いた次世代ハードシェルダウン「Moon Parka ムーンパーカ」がリリースされる。
“アンタークティカ=南極大陸”をも遥かに超える“究極の極地=月”を目指して、その挑戦の道は続いていくのである。
“Never Stop Exploring(探検をやめるな)”という揺るぎないマインドのもと一切の妥協を許さず、高機能を追求し、テクノロジーの限界に挑戦し続けてきたザ・ノース・フェイス。

この【前編】では我々が惹かれる理由のひとつである、日常生活ではオーバースペックなまでの“ファンクションの追求”に焦点を当ててきた。だが、それだけではここまで世界中の人々に愛されるブランドにはならない。
では、それ以上に何に惹かれるのか。ストリートで獲得してきたプロップスとストーリー性。そこに僕らは惹かれるのではないだろうか。続く【後編】では、ファッションやカルチャーと繋がるザ・ノース・フェイスの魅力を掘り起こしていく。