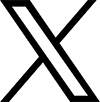女性を魅了し続ける人気デザイナーズブランドの世界。 〈コム デ ギャルソン〉〈メゾン マルジェラ〉〈ディーゼル〉ほか
ファッションとひと口にいっても、カジュアルなものやアウトドアテイスト、エレガントなものなど、いろんな系統やカテゴリーがあります。特に洗練された女性たちから支持を集めているのが「Designer’s Brandデザイナーズブランド」。そこで今回『knowbrand magazine』では、女性を魅了し続ける人気のデザイナーズブランドを厳選してご紹介します。
「knowledge is power知は力なり」という言葉があるように、ファッションもまた、知識を持つことでより深く楽しむことができます。ブランドのルーツや背景にあるカルチャーを知ることで、いつものアイテムが特別な存在に変わり、毎日のコーディネートやモノ選びに奥行きと説得力が生まれるはず。そこで、ちょっとしたウンチクも合わせてご紹介しますので、少々お付き合いくださいませ。
まずは知っておきたい基礎知識。
ところで、デザイナーズブランドとは?
ちょっぴりウンチクも。
そもそも「Designer’s Brandデザイナーズブランド」という言葉が広く使われるようになったのは、1980年代中頃のこと。当時、日本国内で一大ブームを巻き起こした「DCブランド」という言葉をご存知でしょうか?これは、デザイナーズブランドと「Character’s Brand キャラクターズブランド」を合わせた略称で、ほぼ同じ意味として扱われていました。
デザイナーズブランドの特徴は、創立者であるデザイナー本人の個性が際立つ、創造性豊かなアイテムを展開している点です。ブランドの世界観から商品の企画、コレクションの展開に至るまで、デザイナーの哲学や美学が色濃く反映されています。多くの場合、デザイナー自身の名前がブランド名として用いられるのも特徴です。
一方、キャラクターズブランドは、ブランドそのものの個性(キャラクター)を重視し、デザイナーの名前を前面に出さない傾向があります。1970年代後半にデザイナーズブランドとの差別化を図るために生まれましたが、1980年代に入ると両者は一体化し、DCブランドとして一世を風靡しました。
1980年代前半のDCブランドブームの最盛期には、「ラフォーレ原宿」や「渋谷パルコ」がファッションの聖地として賑わい、「ハウスマヌカン」と呼ばれたショップ店員は、憧れの職業として注目を集めました。バブル景気前夜の拡大する消費の中で、DCブランドブームは地方都市へも波及。ファッションビル「マルイ」などを通じて全国的な広がりを見せたのです。
インターネットやSNSが存在しなかった当時、この一大ブームを牽引したのが、ファッション雑誌『anan アンアン』や『POPEYE ポパイ』。最新のファッションやカルチャー、ライフスタイルを発信するこれらの雑誌が時代のトレンドセッターとして若者たちのファッション意識を高めていたのです…なんてウンチクもちょっと知っておくと、ファッションを単なる消費としてではなく、カルチャーとして捉え、より深く楽しむことができる…かもしれません。
さてさて随分と前置きが長くなりました。ぼちぼち本題の女性を魅了し続ける人気のデザイナーズブランドのご紹介といきましょう。
絶対に外せない!
日本が誇るデザイナーズブランド御三家 +α

世界には数多くのデザイナーズブランドが存在しますが、日本が誇るトップブランドにフォーカスを当ててみましょう…、となれば、まずは絶対に外せない3つのブランドからご紹介します。
〈ISSEY MIYAKEイッセイミヤケ〉
一枚の布から生まれる革新的なデザイン

トップバッターは、〈ISSEY MIYAKE イッセイ ミヤケ〉。デザイナーの三宅 一生は、多摩美術大学在学中から、衣服を単なる「ファッション」ではなく、普遍的な「デザイン」として捉えていました。1960年の「世界デザイン会議」で衣服の分野が含まれないことに疑問を呈したエピソードは、彼の姿勢を象徴したエピソードです。パリでの「五月革命」に遭遇したことが転機となり、特別な人のための高級なオートクチュールではなく、より多くの人々が自由に動きやすい服を作ろうと決意。1970年に「三宅デザイン事務所」を設立し、1971年にはイッセイミヤケとしてニューヨーク コレクションに参加しました。
「一枚の布」という独自のコンセプトのもと、生地をできるだけ捨てずに使い、布と体の間に空間を生かした「デザインとしてのファッション」を追求する姿勢は、世界中のデザイナーに大きな影響を与え続けています。

〈Pleats Please プリーツ・プリーズ〉の象徴的なテキスタイル。
イッセイ ミヤケには多くの派生ブランドがありますが、中でも1994年春夏シーズンにスタートした〈PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEプリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ〉は、ブランドを象徴する存在です。1988年のウィメンズコレクション「プリーツ」を発展させ、糸から開発した素材を「製品プリーツ」という独自の技法を駆使したアイテムは、美しいシルエットで軽く、着心地も良く、洗えてシワにもなりにくいという機能性の高さで絶大な人気を誇っています。イッセイ ミヤケの世界観を体感したいと思ったら、まずはプリーツ・プリーズが「間違いナシ!」といえるでしょう。
(→〈プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ〉をオンラインストアで探す)
〈COMME des GARCONS
コム デ ギャルソン〉
反骨精神の美学を貫く稀代のブランド

続いては、日本が世界に誇るデザイナーズブランドとして、多くの人が思い浮かべるであろう〈COMME des GARCONS コム デ ギャルソン〉です。
デザイナーは、川久保 玲。1964年に慶應義塾大学を卒業後、大手テキスタイルメーカーに入社し、繊維宣伝部でスタイリストの経験を積まれました。意外にも、彼女は服飾系の学校出身ではありません。その後、1967年からフリーランスのスタイリストとして活躍。自らデザイン、パターン、縫製を手掛けるようになり、1969年にコム デ ギャルソンをスタートさせました。
1973年には、株式会社「コム デ ギャルソン」を設立し、1975年には東京コレクションに初参加。当時のファッション界では敬遠されがちだった「黒」を大胆に取り入れたアイテムは人気を呼び、1980年代には、おかっぱ頭で黒服に身を包んだ「カラス族」と呼ばれる人々を生み出しました。
コム デ ギャルソンにも多くのブランドが存在しますが、中でも“ガーリー”と表現されることの多い〈tricot COMME des GARÇONS トリコ・コム デ ギャルソン〉は、フランス語で「編み物」を意味する「tricot」の名前が示す通り、当初はニット類に特化したブランドとして1981年にスタート。その後、展開アイテムを増やしながら、渡辺 淳弥を経て、デザイナーが栗原 たおとなった現在では、フルラインを展開するブランドとして人気を博しています。
また2002年に登場した、ギャルソン初のワンポイントブランドである〈PLAY COMME des GARÇONS プレイ・コムデ ギャルソン〉は、他のラインに比べてリーズナブルかつキャッチ―な印象で人気を集めています。「デザインしないこと」がコンセプトで、ポーランド人デザイナーのフィリップ・パゴウスキーによるハートアイコンをアイデンティティとし、平和的なニュアンスで見る人をハッピーな気持ちにしてくれます。

ガーリーな〈tricot COMME des GARÇONS トリコ・コム デ ギャルソン〉とキャッチ―な〈PLAY COMME des GARÇONS プレイ・コムデ ギャルソン〉。
ちなみに「COMME des GARCONS」とは、フランス語で「少年のように」という意味。デザイナー自身の名を冠するブランドが多い中で、それをしなかった理由は「ただ言葉の響きが好きだったから」だといわれています。後に川久保 玲は「なるべく作った服が表に出て、作った人は表に出ない方がいいと単純に思っただけ」とも語ったとか。いずれにしろ、純真無垢な少年のように、既成概念にとらわれず、反骨精神をもって挑戦的なアプローチで常に新しい表現を探求し続けている姿勢こそが、誕生から半世紀以上が経った今もコム デ ギャルソンが私たちを魅了し続けている理由なのかもしれません。
(→〈トリコ・コム デ ギャルソン〉をオンラインストアで探す)
(→〈プレイ・コム デ ギャルソン〉をオンラインストアで探す)
〈Y’s ワイズ〉
独創的ながら機能的かつ品位ある
女性のための日常着

3つ目にご紹介するのは、〈Y’s ワイズ〉です。デザイナーの山本 耀司は、コム デ ギャルソンの川久保玲と同じ慶應義塾大学を卒業後、洋装店を営んでいた母の勧めで文化服装学院を経てパリへ遊学。その後、1972年にワイズを立ち上げました。
「男性の服を女性が着る」をコンセプトに、機能的で品位ある日常着を作るワイズのアイテムは、体のラインを強調しないジェンダーレスでユニークなパターン、独特なシルエットで、着る人それぞれの個性を引き出してくれます。

〈Y‘s ワイズ〉といえば、美しく品のある黒。
ワイズの独創的なデザインは、まるで着る人の内面を映し出す鏡のようでもあり、だからこそ時代を超えて多くの女性の心を掴み続けているのでしょう。
1981年、山本 耀司は「アンチテーゼによってモードを制覇する」という哲学を掲げ、自身の名を冠したワイズよりもハイエンドなコレクションラインとして〈Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト〉をスタートさせました。1982年には、コム デ ギャルソンと共に全身を黒一色で覆ったコレクションでパリコレデビューを果たします。死や反抗の意味を持つ黒は、当時のモード界ではタブーとされていただけに、このコレクションは「黒の衝撃」と呼ばれ、賛否両論を巻き起こしたことは有名なエピソードです。
また、これまで紹介したイッセイミヤケ、コム デ ギャルソン、ワイズ(またはヨウジヤマモト)は、「日本ファッション界の御三家」ともいわれるだけに、デザイナーズブランドを語る上では絶対に外せないブランドといえます。
〈HYSTERIC GLAMOUR
ヒステリックグラマー〉
ロックやサブカルチャーの趣味的追求

そして+αとして、先ほどの御三家とは少しタイプの違う、日本発のデザイナーズブランドをご紹介します。それが〈HYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマー〉。デザイナーを務める北村 信彦は、東京モード学園を卒業後、在学中からアルバイトをしていたアパレルメーカー「オゾンコミュニティ」に入社。そして21歳の若さで立ち上げたブランドがヒステリックグラマーでした。ウィメンズブランドながら、北村信彦が影響を受けたロックやサブカルチャー、古着やミリタリーの要素を取り入れた趣味的ともいえるアイテム展開で、瞬く間に若者の支持を獲得し、熱狂的なブームとなりました。
シンガーソングライターのパティ・スミスのヒステリックな雰囲気と、ロックバンド「ブロンディ」のボーカル デボラ・ハリーのグラマラスな感じをイメージして、ヒステリックグラマーというブランド名を思いついたというのもユニークですよね。

通称〝ヒスガール〟と呼ばれる女性のイラストはブランドのシンボルとなっている。
ブランド設立から40年を経たヒステリックグラマーですが、近年はY2Kスタイルのトレンドもあり古いヒステリックグラマーのTシャツを収集する20代女子もいるようで、若年層から往年のファンまで幅広い人気をみせています。
大人の女性を魅了する
デザイナーズブランド

続いては、デザイナーズブランドでありながらも、シンプルなルックスとエレガントさで大人の女性を魅了するブランドを3つご紹介します。
〈Maison Margiela
メゾン マルジェラ〉
常識を覆す
革新的でミステリアスなブランド

まずご紹介するのは、四隅を糸で留められた数字が並んだ白いラベル、そしてどこかミステリアスな雰囲気を持つ〈Maison Margiela メゾン マルジェラ〉です。
1988年、デザイナーのマルタン・マルジェラによってパリで設立され、1989年パリ・プレタポルテ・コレクションでデビューを飾ると、それまでのトレンドを覆すタイトなシルエットや、衣服の再構築といったコンセプチュアルな手法で、ファッション界に大きな衝撃を与えました。マルジェラのスタイルは、「脱構築=デコンストラクション」や「デストロイ・コレクション」と称され、古着の活用や加工など独自の視点からの服作りは、多くの人々に影響を与えたのです。

日本の伝統的な足袋から着想を得たブランドのアイコンのひとつでもある「タビ」シューズは、長く愛される定番アイテム。
マルジェラは、1998年春夏にはコム デ ギャルソンとのコラボレーションを行い、1998年から2004年までエルメスのレディースプレタポルテのデザインも手掛けるなど、その才能は広く認められましたが、2008年に突然引退したとされています。表舞台には顔を出すことがほぼなく、写真もほとんど存在しておらず、四隅を糸で留めたラベルには0から23までの24の数字のみが記されているだけでブランド名さえない…。そんな匿名性やミステリアスさもメゾン マルジェラの魅力のひとつであり、私たちがこのブランドに惹かれる理由なのかもしれませんね。
〈CLANE クラネ〉
大人の女性のための
洗練された「特別な一枚」

次にご紹介するCLANE(クラネ)は、30代以上の女性に向けたブランドとして2015年に設立されました。デザイナーは、2013年にEMODA(エモダ)を立ち上げた松本 恵奈。その魅力は、スタンダードなデザインに現代的な柄、素材、デザインを取り入れた、新しいフォルムの表現。「特別な一枚」を重視し、着る人の個性を引き立てるアイテムが揃います。シンプルでありながらも、どこか都会的で洗練されたデザインは、大人の女性の日常に寄り添ってくれるはずです。
2016年にはメンズラインCLANE HOMME(クラネオム)もスタートし、ストリート界のカリスマこと藤原ヒロシ率いるfragment design(フラグメントデザイン)とのコラボレーションも発表するなど、その勢いはとどまることを知りません。
若年層の女性を惹きつける
デザイナーズブランド

最後に、ハイプライスなアイテムが多いデザイナーズブランドでありながら、20代を含めた若年層の女性たちからも絶大な支持を得ているブランドを3つご紹介して締めくくりたいと思います。
〈DIESEL ディーゼル〉
リブランディングとY2Kトレンドで
爆発した女性人気

近年、若年層の女性からの高い支持を集めているのが〈DESEL ディーゼル〉です。ディーゼルは、1978年にイタリアで誕生したデニムを軸とするブランドです。創業者レンツォ・ロッソの「世間を活気づけたい」という思いが込められたブランド名は、新たなエネルギー源であるディーゼル燃料に由来しています。

ブランドを象徴する「D」のマークが主張するアイテムにも人気が集まっています。
良質なデニム素材にこだわり、その高い品質とデザイン性で世界中のファンを魅了してきましたが、以前はメンズブランドとしての印象の方が強めだった感も…。しかし2020年、クリエイティブ・ディレクターに就任したグレン・マーティンスのリブランディングにより、コレクションをジェンダーレスなユニセックス提案に切り替えました。彼が提案する1990〜2000年代のムードを取り入れたクリエイションやスタイリングがY2Kトレンドにマッチし、K-POPアーティストたちが着用したことも影響し、若年層から高い支持を集めるようになったのです。街中でディーゼルのデニムバギーパンツや「D」のロゴが大きく入ったアイテムを着用する女性が多いのも納得ですよね。
〈Vivienne Westwood
ヴィヴィアン・ウエストウッド〉
パンク精神を宿す、反逆のアイコン

続いては、パンクファッションを背景に持つ、イギリスを代表する〈Vivienne Westwood ヴィヴィアン・ウエストウッド〉です。その歴史は1971年、ヴィヴィアン・ウエストウッドがロンドンのキングスロードに開いたショップ「レット・イット・ロック」から始まりました。その原点はイギリスのパンクバンド「Sex Pistols セックス・ピストルズ」の仕掛け人マルコム・マクラーレンのためにデザインし服。そして、マルコムがセックス・ピストルズに彼女の服を着せて世に送り出したことで一躍有名に。挑発的なメッセージ、ストラップやジッパーを多用した過激なデザインは、パンクファッションの代名詞となり、当時の若者たちの心を掴みました。そして1981年に初のランウェイショーを実施し、1983年にはパリコレクションに進出して以降、力強いコレクションを展開しつづけています。
日本でもアーティスト椎名 林檎の1999年の楽曲『本能』のMVや、のちに映画化もされた矢沢 あい原作の人気漫画『NANA』で、ヴィヴィアンの「アーマーリング」などが着用されたことで、大人気に。

王冠と地球をモチーフにした「ORB オーブ 」がブランドのアイコン。
2006年には、イギリス人デザイナーとして初めてエリザベス女王から大英勲章「Dame デイム」の称号を授与されたヴィヴィアン・ウエストウッド。2022年、彼女は惜しまれながらこの世を去りましたが、反骨精神や自由への渇望、そして彼女の精神が込められたアイテムを身に着けることで、これからも私たちに自分らしさを表現する力を与えてくれるはずです。
(→〈ヴィヴィアン・ウエストウッド〉をオンラインストアで探す)
〈MM6 Maison Margiela
エムエム6 メゾン マルジェラ〉
日常を彩る、ジェンダーレスな遊び心

3つ目は〈MM6 Maison Margiela エムエム6 メゾン マルジェラ〉です。先ほど紹介したメゾン マルジェラのコレクションは、コンセプトによってグループ分けされ、ナンバリングされているのが特徴なのですが、その中で数字の「6=女性のための衣服(ガーメント)」が独立し、1997年に生まれたのがMM6です。「ready when worn着ることで完成する服」をコンセプトに、メゾン マルジェラの創造性は備えつつもよりカジュアルで普段使いがしやすく、価格も比較的リーズナブルなため若年層の女性からも絶大な支持を得ています。

日本の折り紙をモチーフにした三角形のデザインが人気のトートバッグ「Japanese」。
客年層をはじめ絶大な人気を誇る女性向けのブランドながら、2022年からはオールジェンダーコレクションもスタートしたMM6。もはや性差をも超越した、着ることで完成する服の今後の展開が楽しみでなりませんね。

さてさて、いかがだったでしょうか。今回の『knowbrand magazine』では、女性を魅了し続ける人気デザイナーズブランドの中から、特にオススメのブランドをご紹介しました。どのブランドも、それぞれの個性と魅力にあふれ、あなたのファッションをより豊かにしてくれるはずです。
ファッションは、単なる衣服の選択ではありません。それは、あなた自身の個性を表現する魔法のような手段でもあるのです。お気に入りのデザイナーズブランドを身に纏い、一歩外にでかければ、きっと新しい発見や出会いが待っているはず。
そう、やっぱり“おめかし”は、楽しいのです。